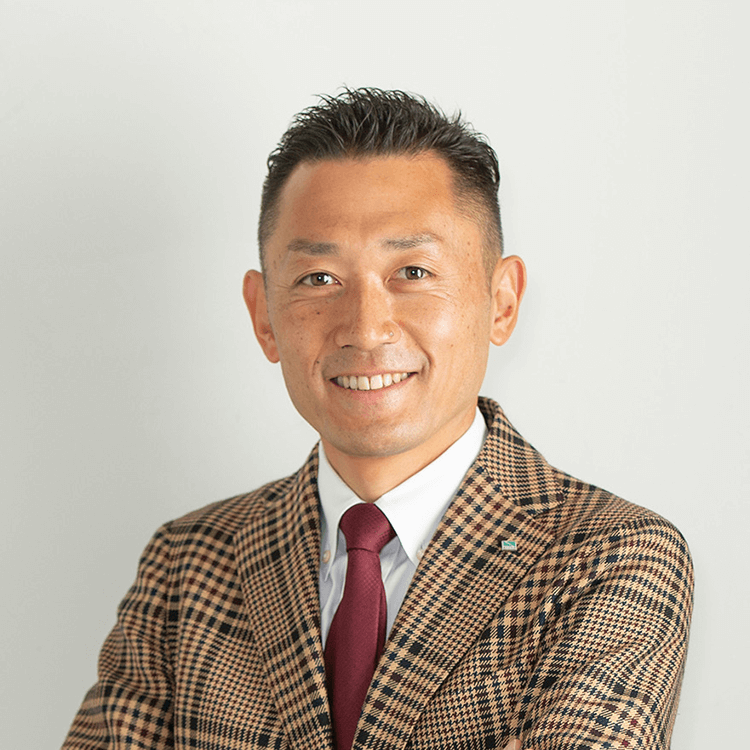「あいつのせいだ」縦割りの悪弊を解消した3代目女性社長の変革 日本の重工業支える産業用ブレーキ企業、「品質だけじゃダメ」の理由とは

日本の重工業を支える電動機用制御ブレーキの専門メーカー「サツマ電機株式会社」(静岡県沼津市)の梶川久美子代表取締役社長は、2013年に父の後を継いで家業に戻り、わずか2年で赤字体質を脱却した。「お客様の信頼に応える製品」という父のモットーを踏まえつつ、品質とともに「サービス」を両輪として捉え、ブレーキ講習会を始めるなど新たな展開を見せてきた。縦割り組織の壁を取り払い、多能工化を進めることで、職場環境や社内の信頼関係も向上させた。会社を変えた3代目女性社長の挑戦について聞いた。
目次
属人化を辞めて「多能工化」へ

──梶川社長は社員の体制改善を行いましたが、改善のポイントはどんなことでしたか?
最も大きな変化は、一人が複数の業務に精通する「多能工化」を進めたことです。他の業務をすることに向いている人から少しずつ、自分の担当以外の仕事も覚えてもらいました。
別の仕事を経験すると、その仕事の苦労が分かるようになるんです。そうやって他者理解が進むと、「あいつのせいだ」という考えが減り、信頼関係が深まっていきました。属人化していることも多かったので、同時に業務のマニュアル化も進めています。
──社員教育への考えにも変化はありましたか?
「人は育てるものではなく育つもの」という言葉に出会ってからは、社員が気持ちよく仕事できる土壌を作ることが大切だと気づき、様々な取り組みを続けています。特に属人化の解消は大きな成果で、これが後の「SV(スーパーバイザー)の派遣」にもつながっていきました。
赤字だった経営を3年で黒字化、社長承継の重責
──代表取締役への就任はどのようなタイミングだったのでしょうか?
2013年に専務として入社して3年後、2016年11月に代表取締役に就任しました。これは入社時から決まっていたことで、「石の上にも三年」とよく言われますが、ちょうど3年でした。
2年間は父と私の2人が代表取締役として並び、私が全てを行うのではなく、銀行対応など対外的な部分を少しずつ父から引き継いでいく期間でした。
──専務と社長の違いを実感されたことはありますか?
本当に違いますね。専務の時は「自分がミスをしても、最終的に父が責任を取ってくれる」という安心感がありました。でも社長になると、あらゆることが「最終的に私なんだ」という重さを感じます。
特に銀行との対応や、クレーム対応など、出てくる場面が格段に増えました。背負っているものの重さは、真正面から見ると重すぎるので、あまり直視しないようにしています。これが「社長は孤独」と言われる部分なのかもしれません。
──赤字だった経営状況はどのように改善していきましたか?
当時の赤字は最大で1,500万円ほどで、私が戻ってきた2013年から2014年にかけては赤字が続きましたが、2015年には黒字化することができました。
好転した理由としては、講習会を始めたことで会社の認知度が上がり、少しずつ受注が増えてきたことが大きいと思います。また、リーマンショックの影響が薄れてきたという要因もあります。
重工業は時代の流れがとてもゆっくりで、リーマンショックの影響が数年遅れてやってきて、その後も長く続いていました。それが2015年頃からようやく変わってきたのです。
──今もお父様は会社にいらっしゃいますか?
父は週に3日ほど会社に来ていますが、ほとんど口を出すことはありません。たまに「お客様対応がちょっとしょっぱい」とか言われることはありますが、年に1回あるかないかですね。基本的には任せてくれています。
製造販売だけではない。「困ったらサツマ電機に相談」
──「お客様の信頼に応える製品とサービス」というモットーについて教えてください。
父は長年「お客様の信頼に応える製品作り」と言い続けてきました。これは重工業では当たり前のことです。
ただ、今はいい製品を作るだけでは足りないので、私はそこに「サービス」を加えました。目に見えないソフト面のサービス展開が私の仕事だと思っています。
──社員の皆さんへも周知が必要だったのですね。
父の時代は社歴の長い人が多く、阿吽の呼吸で仕事をしていました。しかし若返りを図るなかで、何も言葉になっていない理念や考え方を経営指針書として明文化し、共有するようにしました。入社してくる社員には初日にこれを説明し、「製品だけでなくサービスもやる会社」という理解を促しています。
──具体的にどのようなサービスを行いましたか?
具体的な取り組みとして始めたのが「ブレーキの講習会」です。私が入社後に営業でお客様を回ると、お客様側の技術承継問題が浮き彫りになりました。
団塊世代の退職で技術が抜け落ちる、優秀な社員は海外に転勤になる、アウトソーシング化で社内に技術が残っていない、など。そのため、ブレーキのメンテナンスひとつとっても、対処できなくなっているのです。
──講習会の内容と効果について教えてください。
講習会では基礎理論を教えるだけでなく、実機を使って手を動かすことを重視しています。ブレーキはネジを締めればいいというものではなく、全体のバランスの中で加減が必要です。それは机上では教えられません。
また、取扱説明書は1つの製品に1種類ですが、使用環境によって起きる問題は異なります。そこで、ユーザー別のニュースレターを郵送し、トラブル事例や対処法を紹介しています。講習会を通じて「困ったらサツマ電機に相談してください」という流れができてきました。
お客様から直接「困りごと」を聞けるのはビジネスチャンスであり、製品開発や事業方針にも活かせる生きた情報です。「御社の製品は壊れませんね」といった良いフィードバックも得られますし、他社製品との比較情報も聞けます。
──印象に残ったエピソードはありますか?
特に印象に残っているのは、日本製鉄やJFEなどの大手企業の方々が作業服を着て当社の小さな工場に来てくださることです。講習会を通じて彼らが「ああでもない、こうでもない」と言いながら製品を見ている姿を、製造現場の社員も目にすることができます。
BtoBの製品はなかなかエンドユーザーからの反応を直接得る機会が少ないので、「溶接がきれいですね」といった言葉を直接聞けることは社員のモチベーション向上につながっています。社長に褒められるより、お客様から褒められる方が嬉しいものです。
最近では、SVの派遣依頼も増えています。これを可能にしたのが前述した「多能工化」です。誰かが外に出ても、工場の生産が止まらない体制ができているからこそ、お取引様先での技術支援も行えるようになりました。
「業界の困りごと」も「地域の困りごと」も解消したい
──今後のビジョンについて教えてください。
まずは「サービス」の部分をさらに強化していきたいです。また海外展開も進めていて、これを専門で担当するメンバーを作りたいと考えています。基本的には、業界の困りごとにどれだけ応えられるかが重要だと思っています。
──サービスの強化以外には何を考えていますか?
地域の困りごとに応えるために、工業団地内に保育園を作れないかと考えています。子どもを預けられる場所が近くにあれば、安心して働けますよね。社員の中には子育て世代も多いので、これは人材確保にもつながる話だと思います。
あと、アイデアベースですが介護のデイサービスも視野に入れています。災害時のBCPの観点からも、会社からすぐにピックアップできるのは利点があります。保育にしても介護にしても、自分が働いている近くにいられることは大きな安心感につながります。
──働き方についても力を入れていらっしゃるそうですね。
以前、社員と「どんな会社にしたいか」というワークショップをした時、「給与が高くて休みが多い会社がいい」という結論になりました。確かにそれは理想です。経営者の判断ですぐに実行できるのは「休みを増やす」ことなので、年間休日を124日まで増やしました。
今後は納期とのバランスを見ながら、さらに増やしていきたいと考えています。給与については、3年後か5年後には「この地域より3割高く」したいという目標を経営指針書に掲げています。ただし、これは私だけでなく、社員全員の努力で実現するものなので、共に頑張っていきたいと思います。
将来的には、既存事業は社員に任せて、私は新規事業の開発に時間を割きたいですね。地域のためにも、社員のためにも、もっと働きやすい環境を作っていきたいです。
梶川久美子氏プロフィール
サツマ電機株式会社 代表取締役社長 梶川 久美子 氏
1973年生まれ。女子大卒業後、スポーツアパレル企業に入社。その後、人材業界に転身しキャリアコンサルタントとして12年間活躍。2013年に現在勤めるサツマ電機に専務として入社、2016年11月に代表取締役に就任。「お客様の信頼に応える製品とサービス」をモットーに、ブレーキ講習会などのサービス展開に注力。海外展開や地域の困りごとを解消する事業など、新しい事業展開にも積極的に取り組む。従業員44名、年商5億9千万円の電動機用制御ブレーキ専門メーカーを率いている。
\ この記事をシェアしよう /












.png)