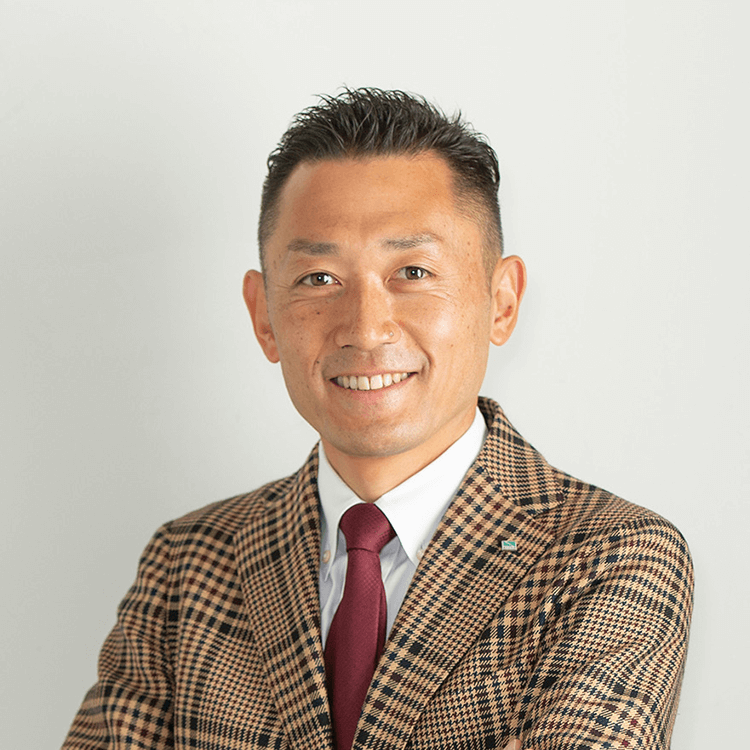売上げ「わずか10%」になった会社、沈没船から逃げるように社員が去った ウイスキーを美味くする、日本唯一の洋樽メーカーを再生した4代目

ウイスキーやワインなどに使われる、国内唯一の洋樽専業メーカー「有明産業株式会社」。4代目の小田原伸行代表取締役社長は、売上90%減となる経営危機の中、父から事業を承継する覚悟を決め、経営改革を経てV字回復に導いた。多くの会社が洋樽事業から撤退する中で、なぜ「お酒造りのトータルサポート企業」へと成長できたのか。「樽の味わい」にこだわり、再生を図った小田原氏の思いを聞いた。
目次
従業員1000人、「将来も安心だな」と思っていた

――創業当時のことや、会社の歴史について教えてください
1963年に祖父が「小田原商店」を創業し、京都・伏見の酒蔵向けに一升瓶用の木箱を製造・販売したところから始まっています。時代の流れとともにプラスチックの箱に切り替わって木箱の仕事は無くなり、大手酒造メーカーの請負業務や物流業を始めました。
多い時には23億円ほどの売り上げがあり、社員は250人、アルバイトも含めると1000人ほどが働いていました。
ところが、派遣法改正で人材の確保が請負から派遣に切り替えられ、請負事業は一気に縮小し、経営が困難になっていきました。そんな中、お酒を熟成するための樽製造の依頼を受け、1984年には宮崎県に工場を建設して製造販売を始めました。
以来、国内唯一の洋樽専業メーカーとして、熟成用の樽の製造販売や海外からの輸入、樽のメンテナンス事業を続け、蒸留所を多角的に支援する体制も構築しています。
――幼少期は家業をどのように見ていたのでしょうか
祖父が創業者で、2代目は長男だった叔父。父は次男で、有明産業の物流部門として運送会社を立ち上げ、木箱を運ぶ仕事をしていました。
幼少期は、よく一緒にトラックに乗っていました。父は肩に木箱を10段くらい積み、トラックにポーンと上手く放り投げるんですよ。それを見て「親父ってすげえ。かっこいいな」と憧れていました。運送会社を継ぐつもりで、「将来トラック乗るんだ」と楽しみにしていました。
ところが、叔父が社長になってすぐ癌が見つかり、2年後に他界。当時学生だった叔父の長男が「継がない」と決断したことで父が3代目の社長になり、私も有明産業の事業承継を意識するようになりました。
当時は大学生。会社はまだ請負で忙しく、冬場の繁忙期に定期的に駆り出されました。学生ながらも社長の息子ですから、「幹部にしてくれ」「給料上げて」などの社員の冗談を聞き、「この人たちが将来自分を支えてくれるんだな。安心だな」と思っていました。
後継ぎのはずなのに「これはおかしい」 逃げ出していく社員

――有明産業の後継ぎを本格的に考えるようになったきっかけは
家業を継ぐだろうと思いつつ、父の意向もあって大学卒業後はフォークリフトの会社に就職します。3年間営業の仕事をしていましたが、「いずれ有明産業に帰るんだ」と思い、当時は甘えた気持ちもあったかもしれません。そんな中で、突然父から電話がかかってきたのです。
「仕事はどうだ」とたずねられ、「慣れてきて面白いよ」と話すと、「水が合ってるなら、そこで骨を埋めろ」と言われたんですね。
「これはおかしい」と感じて母に電話をすると、「実は会社が大変なんだ」と打ち明けられました。派遣法改正で状況がガラッと変わった時期でした。
1社依存で営業もしていなかったので、次の手がない。そんな中で、「営業を経験した自分なら、この状況を打破できるしれない」と思いました。当時は父への反発もあり、「帰ってくるな」と言われたので、逆に帰ることにしました。「苦しい、帰ってきてくれ」と言われたなら、帰らなかったと思いますね。
――入社した時はどんな状況だったのでしょうか
2004年に一般社員として入社し、安全管理や派遣部門の営業の仕事をしました。事業が縮小傾向にある中で、どう立て直すか考えました。自分が状況の悪化を止められると考えていたけれど、実際は止められなかったですね。
そして、2009年のリーマンショックで完全に請負がなくなります。父は運送会社と有明産業を兼務し、実質内情を見ていたのは番頭さん。銀行との交渉も担っていて、「2年かけて教えるよ」と言われていたので心強かったです。
なのにある日、その人が社長室から出てきて、「1ヶ月後に辞める」と言い出しました。おそらく父と喧嘩をしたのでしょう。一つも教わらないまま、その人はいなくなってしまったのです。
父には頼れず、何も知らない自分だけで考えながら会社を動かさなきゃならない。引き継ぎ書を見ながら必死で財務を勉強しましたが、大変だったのは銀行交渉でした。
借金があり、銀行からは「あなたの会社はグレーだ」と言われる始末。業績の急激な悪化で、社員もみんな沈む船から逃げるネズミのように辞めてしまいました。
「悪の親子」と思われても、もう一度「樽」にかけた理由
――厳しい状況の中で事業承継しようと思われたのはなぜでしょうか
会社の売り上げが1/10になった時、どうにもできず、社員の給料を削減し、賞与をなくしました。宮崎の樽工場の人たちからすると、父が「悪の大魔神」で、私は「大魔神の息子」。完全に「悪の親子」です。
樽事業をメインにするしかないのに、工場に全く受け入れてもらえない。 そんな中で2010年、父が「5年後、お前に会社を渡す」と言ってきたのです。「いや、こんなどうしようもなくなった会社渡されても」と思いました。そこから毎日喧嘩です。「こんな状態になったのは親父のせいや」と。けれど父も、「しょうがないやろ。運送会社をやってたのに、急にこっちに社長が回ってきたんやから」と反論しました。「俺の人生も狂わされた」というわけです。今となっては父の気持ちが分かりますが、当時は腹が立ちました。
父を恨み、他責にしていましたが、ふと思ったのです。仮に父が業績を上げ、いい時に自分がのこのこ戻ってきて「社長になるわ」と言ったなら、ナンバー2やナンバー3の人たちはどう思うか、と。たとえ状況が悪くても、自分で事業を作った方が、その先もマネジメントできるのではないか。そう気持ちを切り替え、覚悟を決めました。
――「もう一度、樽に懸けよう」と思うきっかけはあったのでしょうか
最初は、新規事業を考えました。樽作りに使うオーク材を使ったお箸やペンです。オーク材は「カシ」と呼ばれることがあり、使うと色が濃くなる。「カシが濃くなる」つまり「賢くなる」。言葉遊びでペンやお箸の商品化を思いつき、「これや!」とメガヒットを確信しました。
京都大学などに営業に行き、「賢くなるペン置いてください」とお願いすると、「ここは賢い人しかいません」と一蹴されました。学問の神様である北野天満宮にも断られ、途方に暮れる日々でした。
京都商工会議所に通う中で、「有明さん、強みが分かっていませんね」と言われ、強みや弱みを棚卸しする「知恵の経営」プログラムに参加することに。そこで、「樽は可能性がある」と再認識しました。
当時は焼酎ブームが過ぎて樽の需要がなく、みんなやめてしまっていた。でも有明産業は、やめるタイミングを逃していた。「うちもやめてしまったら、樽づくりの技術は途絶える」と考え、最後の砦になろうと思いました。
お酒のメーカーに思いを伝えて回りましたが、大半は門前払い。ところが、ある奄美大島の会社で、工場長が歓迎してくれたのです。「うちのメインの商品は、樽で熟成したお酒。樽を作る人がいなくなる中で、あなたたちみたいな若い経営者が樽をやるのは嬉しい。僕らはたくさんは買えないけど、絶やさないでほしい」と。
木箱も請負事業も、「いらん」と言われてなくなった。でも樽には、「必要だ」と言ってくれるお客様がいた。そのお客様のために、事業を残したいと思いました。ただ、メンテナンスを頼んでくれてはいたが、それだけでは事業として厳しい。樽の事業を成り立たせるためになんとしても数を増やそうと、気持ちに火がつきました。
――そこから、どう樽事業を再生したのでしょうか
とにかく工場に通いました。職人さんは相手にしてくれなかったけれど、知識も経験もあり、顧客情報をもっている工場長のそばで「売り上げを上げたい」と思いを伝え続けました。やがて根負けし、理解してくれるようになり、外部のコンサルタントを入れての勉強会や研修会も開催するなど、改革が始まりました。
戦略が当たり、業績が上がって波に乗ってきましたが、2014年にまた苦難がやってきます。アメリカからのオーク材が入らなくなり、樽が造れなくなったのです。そこで、代わりにヨーロッパの木と日本の木が手に入るように手配し、酒造メーカーに謝罪と説明に行くことになりました。その出来事をきっかけに、社長に就任することになったのです。
小田原伸行氏プロフィール
有明産業株式会 社代表取締役 小田原 伸行 氏
1976年、京都府宇治市生まれ。大学卒業後、フォークリフトメーカーでの営業職を経て、2004年に家業の有明産業へ入社。2008年に取締役、2010年専務取締役、2014年に4代目代表取締役に就任。
(取材・文 ライター・小坂綾子)
\ この記事をシェアしよう /













.png)