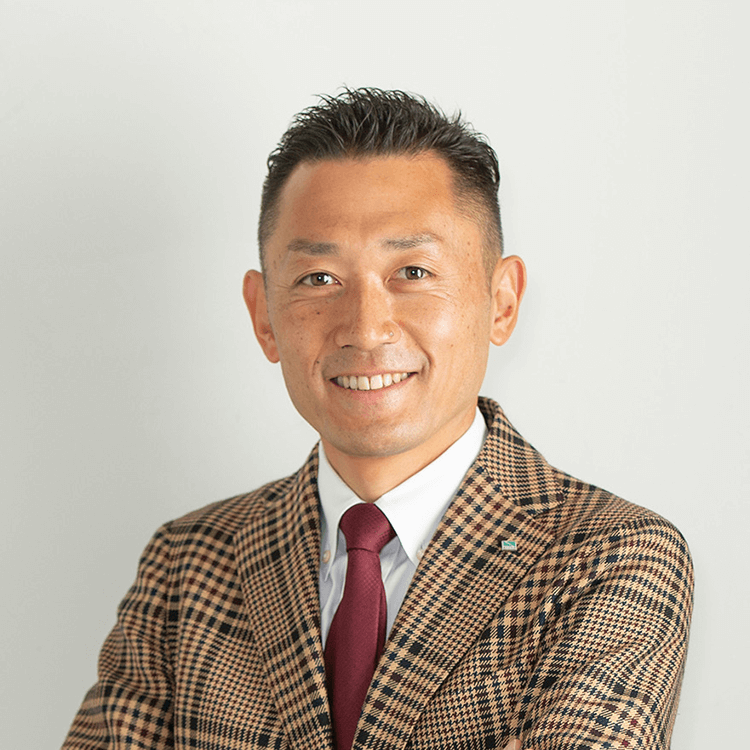「お前が社長になって、説明に行ってくれ」 謝罪から始まった、国内唯一の洋樽メーカーが挑むウイスキー熟成の「トータルサポート」とは

「樽づくりの最後の砦になる」と決め、再起を図った国内唯一の洋樽専業メーカー「有明産業株式会社」。経営危機からのスタートだった4代目の小田原伸行代表取締役社長は、売上90%減の経営危機から、経営改革しV字回復に導き、「樽の有明産業」を「お酒造りのトータルサポート企業」へと成長させて、時代の一歩先を見据えた経営に取り組んでいる。国産材を使用した新樽の製造や、国産麦芽の製造にも挑戦するなど、ジャパニーズウイスキー文化のさらなる発展を目指す取り組みについて聞いた。
目次
「親父は逃げたな」。でも理にかなっていた

――樽の原料となる「アメリカのオーク材」が無い、というピンチから社長の仕事がスタートしたわけですね。どんな気持ちでしたか。
アメリカからのオーク材が入らなくなって、樽が造れなくなりました。そこで、代わりにヨーロッパの木と日本の木が手に入るように手配し、酒造メーカーに謝罪と説明に行くことになりました。
そのとき、社長室で父から「もう俺じゃうまく伝えられない。お前が社長になって、お客様に説明に行ってくれないか」と言われ、4代目の社長になりました。漫画みたいな話です。
父はお客様との交流がなく、樽の材料が変わることについて納得してもらう方法もわからない。その時、初めは「親父は逃げたな」と思ったんですよ。
でも、確かに理にかなっている部分がある。「問題が起こりました。つきましては、3代目の社長は責任を取って退任し、私が社長に就任しました。皆さんご安心ください」と言えるわけですから。そういう経緯で、5年を待たず、事業承継宣言から4年で社長に就任しました。
2009年ごろから銀行取引も担当していて、マネジメントできる感覚はありました。とはいえ、実際に社長になり、ハンコをついたときは、やはりゾクゾクしました。ナンバー2とナンバー1の違いはここにあるんですね。
それまでは、「父が悪い」とか「社長に聞いてきます」と言うことでその場を逃れられたけれど、もう逃れられないし、借金も背負っている。最終責任は自分だとなったとき、「怖い」と思う気持ちがわいてきました。
樽の原料が変わると、醤油とソースくらいウイスキーの味が変わる

――「樽の味わいを提案する」事業が始まったのも、この頃でしょうか
実は、アメリカから樽材が入らないという困難に突き当たるまで、ウイスキーの6割7割は樽の味わいだということを知らなかったのです。
お客様に「国産材のミズナラか、ヨーロッパ材でどうですか」と提案すると、「味が変わってしまう」と言われました。私の提案は、「みたらし団子の醤油が手に入らないので、ソースを持ってきたのでこれで作ってください」と言っているのと同じだったのです。
それに気づいたことから、国産材をシリーズ化し、樽による味わいを提案しようと思い始めました。今まではアメリカのオーク材1本だったお客様に、「調味料は多い方がいいですよね」「塩と胡椒だけでなく、醤油、ソースや味噌、豆板醤があれば、たくさん料理できますよ」という例えで提案すると、複数本購入される。こうしてお客様の単価が上がって行きました。
「樽材が入らない」という問題がなかったら、日本の樽を作ろうとも思わないし、味わいが重要だということも分かってなかったでしょう。
――樽以外の部分でも、新しい事業を始められていますね
私たちは、樽という非常に重要な商品を扱ってるという自負をもつようになり、そこの商品開発を高めてきました。でも近年、「ウイスキーには樽の味わいが6割7割」だとすると、残りの3割4割にあたる酵母や麦芽にもこだわり、100%までお客様の味わいを提案していくことを目指すべきではないかと思うようになりました。
そこで考えたのが、トータルサポートです。日本の樽酒は、麦芽も樽も大半が海外依存ですが、それを国産化すれば、将来的に、もし他国と交易が止まったとしても、お客様がお酒を造れない状況をなくすことができると思ったのです。
日本のウイスキーの価値を高めるために
――トータルサポートの具体的な取り組みについて教えてください
この7月に、ジャパニーズウイスキーの新たな可能性に挑むプロジェクトコミュニティ「We Love Whisky」(愛称Lovesky!!)を、トークンベースの支援プラットフォーム「FiNANCiE」上にオープンさせました。
これまで海外に依存してきた樽や麦芽を日本国内で持続的に供給し、日本ならではのウイスキー文化を育むための「インフラ」になろうという挑戦です。
その第一歩が、国産麦芽の生産です。麦芽は、樽に入れる前の原酒の品質を左右するきわめて重要な要素です。樽だけでなく麦芽の国産化にも取り組むことで、お酒への新たな付加価値を生み出せる。さらに、国内での安定供給を実現することで、ジャパニーズウイスキーの魅力と価値を、より多くの人へ届けられると思うのです。
2027年に北海道に樽工場を建設し、麦芽の製造にも挑戦していきます。簡単ではないと思いますが、お酒はテロワール(風土の個性)の観点があります。地産地消でジャパニーズウイスキーの価値を高めていきたいのです。
「Lovesky!!」は、数年後に生まれる「価値ある一杯」を、蒸留所やサポーターの皆さんと一緒に育てていく一大プロジェクトです。応援の証であるデジタルアイテム「トークン」を集めることで、プロジェクトに参加できます。大麦の成長過程などの情報や体験イベント、抽選企画、限定ウイスキーのプレゼントなど、たくさんの特典を用意しています。
また、パートナー枠では、樽の購入権が得られ、国産原材料100%のウイスキーオリジナルボトル30〜300本のほか、樽にネームが入り、宣伝広告として経費で落とすこともできるなどの特典があります。
複数の蒸留所とタイアップして多様なお酒をファンの方と一緒に作り、国産化を広げていきたい。日本のウイスキーの価値が高まってファンが増えると、きっと、今まで飲まなかった、興味がなかった人にも魅力を伝えられると思うのです。
一つの事業が「10年」しか持たない時代が来た
――事業承継をする上で、大事なポイントはありますか
受け身ではなく、主体性をもって全て完結させていく経験は必要だと実感しています。父から突然引き継ぎを受けて自分でやらなければならない苦労もありましたが、番頭さんから全て教わっていたなら、ここまでできなかったかもしれない。危機的な状況を経験したときに、そこをどう打開していくか、自分で考えて進んできたので新しいことができたのだと思います。
木箱の製造や請負事業は、環境の変化でなくなりました。「一事業30年説」といわれていますが、これだけ移り変わりの早い時代の中で、今はきっと10年ももたない。長くは続かないという前提のもとで、先代からの事業を新たに作り変えたり、次につなげていくためにブラッシュアップしたりする気持ちで臨むことが必要でしょう。常にイノベーションを起こしながら、新しいものをキャッチして次につなげていくことです。
ビジネスは、お客様の問題と課題を解決することですが、それが世の中の課題や問題を解決することにつながっていきます。人間が生きてる以上、負の側面も必ず生み出されるので、我々の今持っている強みや商品が、その負の部分をどのように解決できるのか、これから考えていきたいですね。
小田原伸行氏プロフィール
有明産業株式会社 代表取締役 小田原 伸行 氏
1976年、京都府宇治市生まれ。大学卒業後、フォークリフトメーカーでの営業職を経て、2004年に家業の有明産業へ入社。2008年に取締役、2010年専務取締役、2014年に4代目代表取締役に就任。
(取材・文 ライター・小坂綾子)
\ この記事をシェアしよう /












.png)