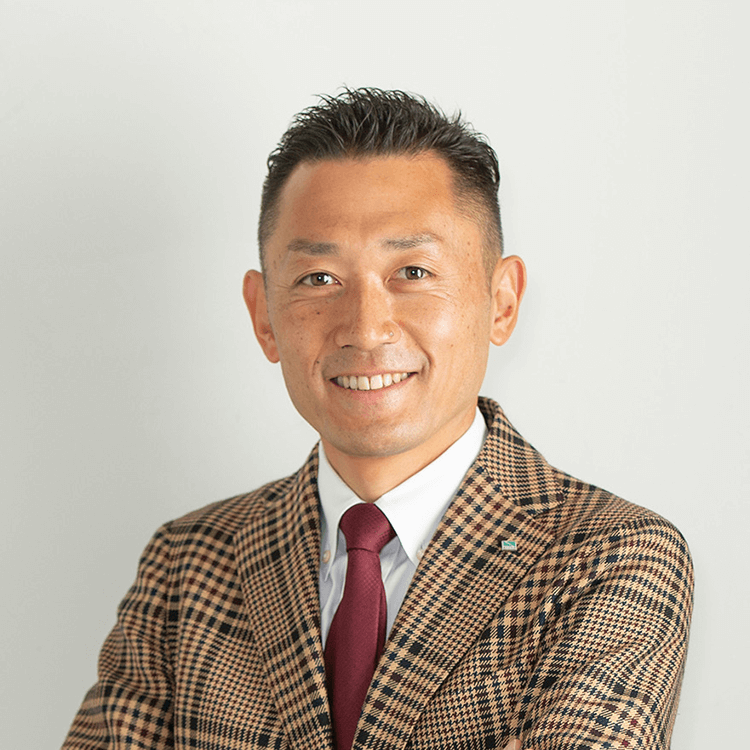「あれ、大事にされてない…?」観光地から塩対応されたご当地銘菓 若き5代目が果たしたリベンジとは

大分県臼杵市に「臼杵煎餅」というご当地銘菓がある。江戸時代の参勤交代で、携行食に用いられたという、生姜の風味豊かな菓子だ。2019年に創業100年を迎えた後藤製菓は、臼杵煎餅のシェア1位。5代目の後藤亮馬代表取締役(34)は、大学卒業後に入社した家業の抱えるさまざまな課題を目の当たりにしてショックを受けた。創業100年の節目に老舗5代目が取り組んだ、思い切った改革とは?
目次
8歳の時に書いた将来像

−−−−小さい頃から家業を継ぐことを意識されていたのですか?
当時、町工場のような自宅横の工場で、毎日煎餅の焼ける匂いを嗅いで育ちました。家業は、当たり前に生活の一部でした。
承継については、洗脳教育をされていた感じです。例えば、8歳の時に将来の自分がどうなっているかを予想した「タイムカプセル」には、「会社を継いでいて、従業員を雇っていて、新しい菓子を作って、商売繁盛、大もうけ…」と書いていました。
振り返ると、本気で継ぎたいというより、周囲に誘導されていたという方が適切かもしれません。今、大もうけ以外は全部実現していますが(笑)。
−−−−大学は地元で進学し、比較的自由に過ごされていたのですね。
親は、大学は猶予期間としてどこでも行ってこいという感じでした。私も、家業に入る以外の道に進みたいという強い気持ちもなく、地元の大分大学に進みました。実家から通っていたので、結局地元から一歩も出ていません。
同級生が就活を始める頃になり、このまま家業に入って大丈夫なのかという焦燥感を覚えました。そこで、通信制の菓子専門学校で学んだり、簿記の資格を取ったりしました。
今までの認識とのギャップに悩む
−−−−大学卒業後の2013年、予定通りに後藤製菓に入社されます。実際に働いてみて、どうでしたか?
工場でパート社員と菓子を製造したり、父と一緒に百貨店や観光地に営業に回ったり、幅広く何でもやりました。顧客回りをすると、今までの自分の認識とのギャップに気づき始めます。
小さい時から、「臼杵煎餅はすごいんだぞ」と教育され、疑っていなかったのですが、実際はどうもそうではない。顧客にとって重要な商品である感じがしませんでした。
品切れしていても、お願いしないと発注すらしてくれません。臼杵煎餅の主な顧客層は60代以上で、若者どころか40~50代にもあまり支持されていない。煎餅は手塗りの工程に特色があるので発信したらどうかと考え、イベントで実演してみても全然反応がなく、がっかりでした。
社内も問題が山積でした。特に労務関係に課題が多く、従業員は有給休暇の「ゆ」の字もないような状況で働き、月末の給与遅延もありました。こんな状態だとは、入社前は全く知りませんでした。
−−−−そういった課題に、どのように対応されたのでしょうか?
外での経験も積まず、無計画に家業に入ったことを後悔しましたが、今更やり直す時間もありません。
中小企業の経営相談に乗ってくれる「よろず支援拠点」という所に、わらにもすがる気持ちで通いつめ、税理士に財務について聞いたり、社労士に労務関係のことを尋ねたりして、必死に勉強しました。また事業引継センターの紹介で後継者育成塾に通い、経営について学びました。
入社から5年ほどの期間は、自己研鑽をしながら課題を一つひとつ解決していきました。
「不易流行」を体現する100周年記念ブランド

−−−−2019年に後藤製菓さんは100周年を迎えました。その節目に向けての取り組みについてお聞かせください。
そのころ、営業活動で自社の説明をした際、ある大学の先生に「それって不易流行だね」と言われました。
父もその先代も、臼杵煎餅という大分県の小さな町の食文化の魅力を少しでも伝えたいがために、さまざまな商品開発や事業をしてきました。
本質は大切に守りつつ、新たなことを取り入れるという意味の「不易流行」という言葉は、会社の在り方を表すのにぴったりだと思えました。そこで100周年の機会に、自分自身で、その「不易流行」を体現した商品を作ることにしたのです。
−−−−具体的には、どのような商品になったのですか?
「IKUSU ATIO(イクス・アティオ)」という臼杵煎餅のブランドを作りました。「大分臼杵」をローマ字にして、逆から読んだ名前です。かわいらしさで若い人にもアピールできるよう、サイズを小さくし、さまざまな味のバリエーションを展開。パッケージの材質や形にもこだわりました。
これが大ヒットし、発売から半年で売り上げは通年比140パーセントを記録しました。新商品だけでなく、既存の臼杵煎餅の売り上げも相乗効果で上がったので、本来伝えたい商品をしっかり伝えることもできました。
職人も新しく6人雇用しました。承継前の一つの成功体験です。
−−−−新商品の開発について、従業員の方や、お父様は、どのような反応でしたか?
いろいろ課題がありました。小さく焼くために型を変えると、数百万円の投資が必要になる上、交換にも時間がかかります。また煎餅には一枚一枚手で蜜を塗っていますが、小さいと熱い蜜が手につきやすくて無理だと言われました。
そこで、直接製造現場に入り、職人と一緒に解決法を探っていきました。職人のように知識や経験などがあまりなかったから、先入観にとらわれずに考えられたかと思っています。
最終的には、既存のラインのまま小さく焼くことが可能になり、蜜を塗る工程も慣れれば問題なく、逆に通常より1人あたりの製造枚数が増えたほどです。
父は基本的には、「やりたいことはやればいい、失敗したら失敗から学べ」というスタンスでした。だから、特に文句をいうことなく、私の思う通りにやらせてくれました。
後藤亮馬氏プロフィール
株式会社後藤製菓 代表取締役社長 後藤亮馬氏
1990年、大分県生まれ。大分大学卒。2013年、実家であり1919年から臼杵煎餅の製造・販売を手がける「後藤製菓」に入社。2019年、100周年を記念したブランドIKUSU ATIOを設立。煎餅製造時の副産物を利用しフードロスを解消したジンジャーパウダーで、農水省のフードアクションニッポンアワード受賞。有機農業の推進、地域社会への寄与などにも積極的に取り組む。本質を大切にしつつ時代に合わせて新たなことを取り入れる「不易流行」の精神に則り、臼杵煎餅の可能性を広げるため日々邁進している。
\ この記事をシェアしよう /












.png)