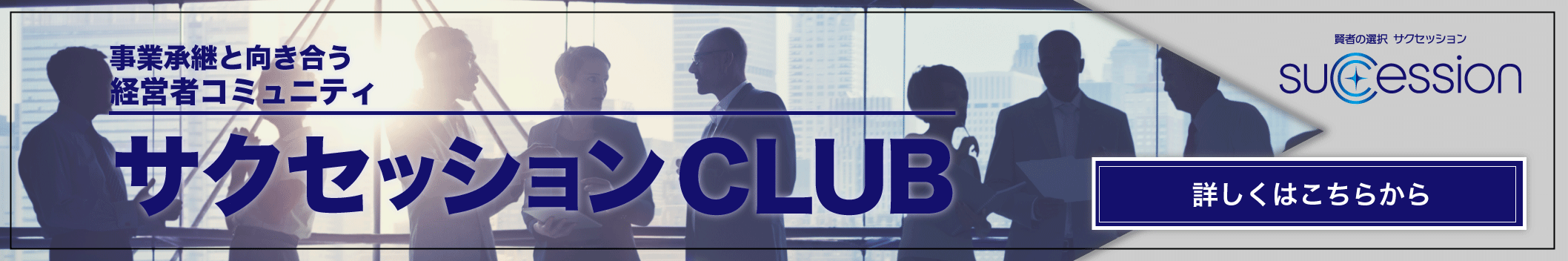COLUMNコラム
「おじいちゃん、おばあちゃんのお菓子」じゃない!脳梗塞を乗り越えた8代目が挑む「煎餅のシズル感」 銀座で220年、老舗が手がける煎餅の再構築とは~松﨑商店【前編】

東京・銀座に創業220年を迎えた煎餅屋がある。関東大震災や東京大空襲を乗り越えた老舗を2018年に継いだのは、8代目の松﨑宗平代表取締役社長だ。就任直後に脳梗塞に倒れながらも、コロナ禍真っ最中に本店を移転したり、イートインスペースを設けたりするなど、大胆な仕掛けを続ける。「おじいちゃん、おばあちゃんのお菓子」を脱却し、「煎餅を再定義し、再構築する」と唱える松﨑社長の「商いのDNA」にインタビューで迫った。
目次
創業220周年を間近に見据えて

――2024年に、創業220周年を迎えます。やはり歴史の重みを感じられますか。
松﨑 日本は老舗が多いですからね。アニバーサリーイヤーではありますが、珍しいとは感じていません。加えて言うと、老舗を武器にはしたくないんです。日本人は価値観を「他人の評価」に左右されがちな人が多いと思っているんです。
「これだけ皆に長く愛されているなら、きっと美味しいんだろう」と、老舗であることがひとつのスパイスになってしまう。本質的に選ばれているわけではないと言いますか、その後ろ盾に甘えているのは健全ではないよなと思っています。
煎餅の「再構築」とは
――煎餅を「再定義」し、次に「再構築」するというのも、ただ老舗の看板に甘えていてはいけないという想いから生まれたのでしょうか?
松﨑 まずあったのは「煎餅は売るのが難しい。どうしたら買ってもらえるのだろうか」という疑問でした。2007年に家業へ入った当時、圧倒的な主力は米菓で、代名詞である絵付きの瓦煎餅「大江戸松﨑三味胴」をはじめ小麦の煎餅の売上は、全体の3~4%ほど。
商売としては切ってもいいのだけれど、なんとか活かせないかと。そこでサンリオをはじめキャラクターとの積極的なコラボや、BtoBやBtoCのマーケットでの展開を試みたんです。やはりギフト需要は非常に強かったですね。
そこでようやく売れるポイントが掴めたので、煎餅という「おじいちゃん、おばあちゃんが食べるお菓子」を、美しくて手渡したくなる「お土産になるお菓子」へと再定義しようと思いました。
実際のところ、こたつの上に煎餅が盛られた器があって……というのは、現代ではすでに失われた風景なんですよね。イメージだけあっても仕方がありませんから、いっそ「お酒を飲みながら煎餅をつまむ」というカルチャーをつくってしまおう、「スナックは煎餅で」という世界にしてしまおうと思い立ちました。
2021年、銀座から東銀座に本店を移し「MATSUZAKISHOTEN」と名も店構えもあらためたのも、その想いを体現するためです。
「シズル感」あふれる煎餅

――ここから、次のフェーズである「再構築」へと移行されていくわけですね。
松﨑 新型コロナウイルスの影響が大きいですね。売上がかなり厳しくなって、会社ももう数年で倒れるという状況でした。再定義だけではなく、プロダクトそのものを構築し直さないと、もっと面白いことはできない。この苦境を突き抜けられないと考えたんです。
再構築にあたって、もっとも意識したのは“シズル感”(※食欲や購買欲を刺激するみずみずしさ)。
煎餅って、メディアで紹介されても反応が鈍いんですよ。みずみずしさやツヤ感がないので食欲をそそられないんですよね。
そうしたマーケティングの視点から生まれたのが、「MATSUZAKISHOTEN」のカフェコーナーで提供している「松崎ろうる」です。柔らかく焼き上げた瓦煎餅に小豆餡やカラフルな白玉を挟んだもので、絵として映える。夏場はかき氷も展開しています。
――煎餅屋という枠組みや伝統を大きく揺さぶる試みですね。家業に入られる前は、ITベンチャーでアートディレクターを務められていましたが、その経験も生きているのでしょうか?
松﨑 店舗やパッケージのデザイン監修という、スキルとして役立っています。私はITベンチャーにしろ煎餅屋にしろ、仕事のやり方は全て同じだと思っているんです。販売、営業、社長の私に至るまで、スタッフがやるべきことはごくシンプル。
物事をきちんと分析して課題を見つめ、強みを伸ばす……その継続です。見た目や店構えから革新的とよく言われますが、中身は超保守的なんです(笑)。
脳梗塞、コロナ…波乱のなかでの「本店移転」
――ITベンチャーから煎餅屋への転身はギャップもあったのではないですか。
松﨑 パソコンすらありませんでしたし、メールアドレスは父と営業、工場の3つだけ。会社のロゴがほしいと言えば、紙の原本をぺらっと渡されて(笑)。
すべてが衝撃的だったので、IT関係の整理から始めました。
ホームページも当初は私一人でつくって運営していました。社員との交流の面でも、始めは私もITベンチャーでの言い回しが抜けず、横文字だらけの言葉でダーッと話していて……あれは嫌がられただろうなあ。「松崎商店での共通言語」を徐々に会得していきました。
――社長に就任されたのは2018年ですね。
松﨑 ええ、でも翌年に脳梗塞で倒れて2ヵ月ほど入院したんです。言葉もうまく喋れないし半身も軽く麻痺してしまって、社長業らしいことといえばハンコを押すくらいでした。退院後、いよいよ仕事を頑張らねばというタイミングでコロナが始まり……思えばずっとドタバタしていましたね。
社員に自分を知ってもらうことが将来を左右する
――まさに波乱万丈ですが、コロナ禍で本店を移転するという判断は社内でどう受け止められたのでしょうか?
松﨑 スタッフも「店舗を閉じるのはわかる。でも移転してさらに面積を広げるなんてどういうことなのか」と驚いたでしょうね。ただ、反対の声はなかったですね。要所要所の社員には事前にしっかり話していましたから。いきなり判断をくだしたわけではありません。
やはりファミリービジネスにおいては、こと、コミュニケーションが重要だと思います。社長にはなれても、周囲が納得するかといったらそうではない。下積みも何もなしに、まったく違う畑からやってきた人間がいきなり役員になったらなおさらです。だからこそ、積極的に話すなり喧嘩するなり、社員に自分を知ってもらうことが今後を左右する。
あとは表面的に取り繕わないことですね。つじつまが合わないことを口にすると、一気に信頼を失ってしまう。知識がないならそれを説明して「わかりません」でいいわけです。私も工場のことは一切知ったかぶりしません。自分に正直に、考えをしっかりと積み立てた上で言葉を使う。自分が納得したことしか言わない、やらないというのは血かもしれませんね。父もすごく頑固でしたから。
(文・構成/埴岡ゆり)
※こちらの記事は追記・修正をし、2024年2月18日に再度公開しました。
後編|「お酒と煎餅で」銀座のサードプレイスを目指すバンドマン社長/創業220年の煎餅店、明治時代も「夜な夜な街の爺婆を集めて…」~松﨑商店
SHARE
記事一覧ページへ戻る