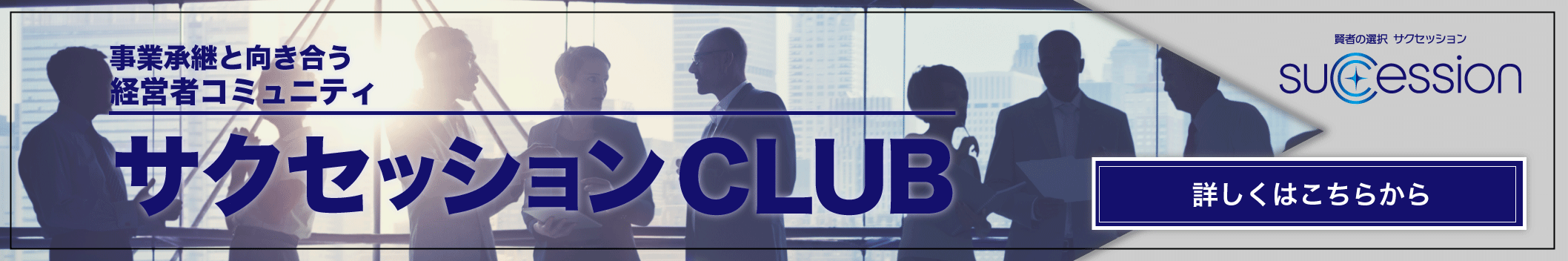COLUMNコラム
苦情から逃げる上司、専務お気に入りが出世 「とんでもないとこ来た」孤立した創業者のひ孫 東京・銀座で119年続く文房具専門店の跡継ぎストーリー

東京・銀座に創業119年の文房具店がある。老舗の看板を守っているのは、創業者のひ孫にあたる5代目社長だ。入社当時、生え抜きの専務が支配する組織で冷遇されつつも、「派閥」を解消して社長に就任。老舗ブランドの価値を落とさず、クリエーティブな社風を育んできた。日本の一等地で商いを続ける文房具店「伊東屋」の事業承継を、伊東明社長(59)に聞いた。
伊東屋…1904年、伊東勝太郎氏が銀座3丁目に「和漢洋文房具店伊東屋」を開業。関東大震災と東京大空襲による店舗全焼を乗り越え、オリジナルブランドを始めとする高級筆記具や画材を販売する。2005年から5代目の伊東明氏が社長を務める。社員数289名人(2020年7月現在)。本社は東京都中央区。
目次
「跡継ぎ」か、カーデザインか
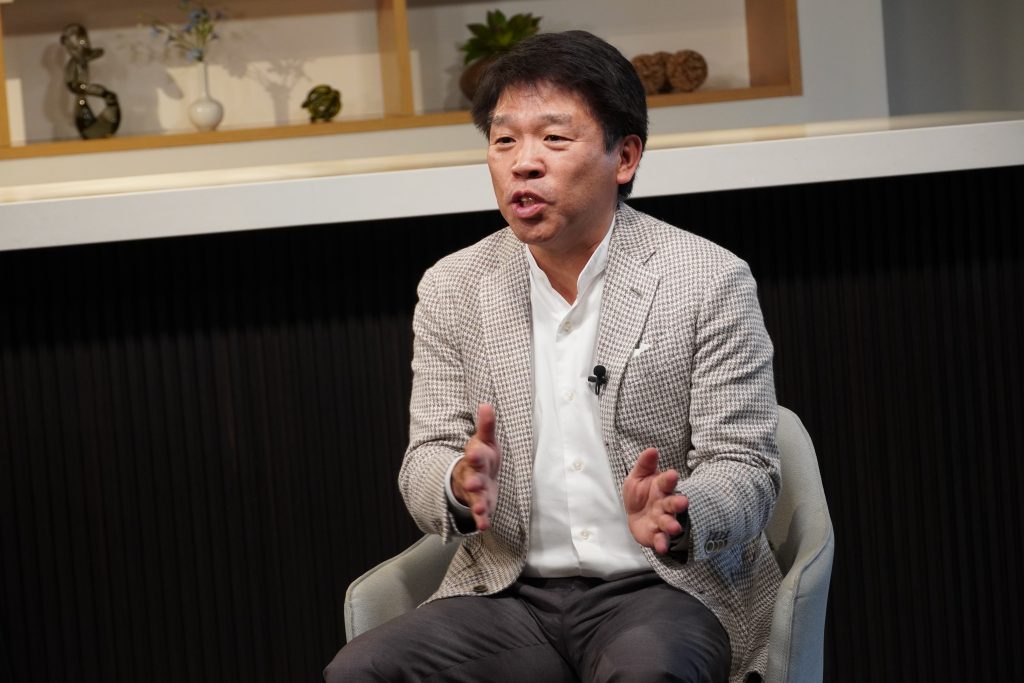
――5代目社長ということですが、創業者と伊藤社長の関係を教えてください。
伊藤 創業は伊東勝太郎という、私の曽祖父です。2代目は、祖父・義孝が継ぎました。勝太郎の娘が4人おり、長女と結婚したのが義孝です。義孝夫妻の長男が、3代目社長の父・恒男です。父が早く亡くなり、父の弟・髙之が4代目となりました。
――将来、自分も伊東屋を継ぐと思ったのはいつのことですか。
伊藤 幼稚園の頃、大きくなったら「跡継ぎ」という仕事になると思ってました(笑)。「あなたは跡継ぎでしょ」って言われて。お友達のお母さんとか、親戚からですね。
小中学校、大学と、家業を継ぐことは頭の片隅でずっと意識してました。でも、小学生の頃、父が本当に急に死んじゃったんです。まだ祖父は元気でしたが、80歳を過ぎていたので、叔父を呼び戻したんですね。
叔父の娘が、私より少し年上で、銀行員と結婚していました。銀行員が会社を継ぐって話をよく聞くので、そういう人を婿さんにもらったのかな、跡取りになるのかなって気はしてました。
――それでも、後を継ぐことはずっと考えていたのですか。
伊藤 いや、実は車のデザインをしたかったんですよ。絵が好きで、スポーツカーの絵を描いて、もっと格好良く描こうとか考えていたら、車のデザインという仕事を知りました。そんな素敵な仕事があるのかと喜んで、これになろうと。中学3年の時です。
アメリカに車のデザイン学校があって、通うためには英語を勉強しなきゃいけない。高校3年時、交換留学で1年、アメリカに留学し、その後慶応大に入学しました。
在学中もアメリカやスイス、イギリス、イタリアでカーデザインの学校やデザインファームを訪ね歩きました。でも、母親が慶応はやめさせてくれない。いよいよ、アメリカの学校に戻ろうと決め、母に伝えたら「出してあげるお金はない」。そこで、伊東屋の4代目社長の叔父にスポンサーになってほしいと頼みに行きました。
――伊東屋の跡取りと言うより、かなりデザインの道に傾いていますね。
伊藤 そうですね。でも、叔父にはアメリカに行くなら伊東屋に籍を置けと言われました。肩書は伊東屋社員。でも、何年かはデザイナーをやれると思っていました。叔父の娘婿が継ぐ可能性もあったから。
その後、アメリカのデザイン学校を卒業しましたが、卒業の数カ月前にバブルがはじけました。日本から連絡が来て「日本の景気がおかしくなりそうだから、帰ってきて会社で仕事をしなさい」って言われまして。平成元年。運命が決まってしまいました(笑)。
「とんでもないとこ来た」出世のポイントは専務に気に入られること
――伊東屋に入社した直後は、どのようなお仕事を
伊藤 まずは売り場のスタッフです。当時、店舗にコピーコーナーがあり、今だと考えられないですがカラーコピーが普及しておらず、A1が1枚6千円もしました。収入になるのですが、コピー取りって面白い話じゃないですよね。慶応の友人に、お茶くみになったのってからかわれたりしました。
ちょっと変なエピソードですが、入社直後、カウンターでお客さんが「コピーを丸めて」と頼みました。普通はくるくるっと棒状に丸めるとこですよね。でも、対応した新人の男の子は「丸めていいんですか」って聞いた後、ぐしゃっと(笑)。
で、売り場奥のマネージャーを見たら、ぱっとしゃがんでカウンターの下に隠れました。僕は、すっ飛んで行って「申し訳ございません」と謝りましたが、「なんてとこ来ちゃったんだろうな」って思いました。
――困った上司ですね。今のエピソードが象徴的かどうか分かりませんが、社内の雰囲気や風土はどうでしたか。
伊藤 簡単に言うと「ひどいな」ですね。父(3代目)の頃の伊東屋はすごく楽しかった。たとえば、ラジコン飛行機の売り場があり、今でいうDIYのコーナーもあった。
でも、入社時の伊東屋は、たとえば売り場の蛍光灯カラーがバラバラだった。何の事かというと、蛍光灯は色温度があり、黄色から青までありますが、何を売るかによって色を合わせないといけない。蔑ろになっていて、何かよくない感じがしました。
加えて、先ほどのマネージャーが隠れる事態があったので、「いったい、どんなことになってんだ」「やりたくないな」と思ったのが正直なとこですね。
――当時、社長になると既に考えていたのですか。
伊藤 やらなきゃいけなくなるだろうとは思ってました。当時、叔父の娘婿は伊東屋に来ていなかったので。ただ、誰にも言われてなかったし、会社の先輩や同僚は、冷たかったですよ。
女子社員は、ものすごく意地悪でした。他の人より特にきつい言い方をされたし、男性の先輩は、僕と関係を持つことがマイナスになると思ってたみたいで話もしてくれませんでした。
――オーナー直系の方と仲良くなると、社内でアドバンテージが出るように思いますが。
伊藤 当時、叔父が社長でしたが、実権を全部握ってる専務がいました。専務は、叔父よりも年上で、彼の派閥がありました。専務にいかにかわいがられるかが、出世の一番大事なポイントだったのです。
もう一つは、叔父に娘婿がいたので、どっちが社長になるか分からないから、色をつけないように日和見していた人もいたのでしょう。だから僕は冷や飯を食ってましたね。
希望がない…硬直化した会社をどうやって変える?

――どのように社長への青写真を描いたのですか。
伊藤 青写真は何にもなかったですよね。もう言われた通りのことをやるしかない。本当に希望がない感じでした。閉じ込められたような感じ。ただ、パソコンが普及し始めていたので、IT化は急務でした。
たとえば、インスタントレタリングという印刷商材があったのですが、1枚数千円で高価格でした。当時、ポスター作成の必需品で、電通とかが大量に買っていましたが、アメリカではマックで代用できる時代になりつつありました。
インスタントレタリングは、1日150~200万の売り上げがありました。でも、もう次を考えておかなきゃいけない。専務たちに言うと、「アメリカで起こったからといって、日本で起こるものではない」「何年か後に来るだろうけど、今は先の手を打つ必要はない」。
――なかなか硬直化した空気だったのですね。
伊藤 はい。ただ、硬直した雰囲気をスルーせず、自分が変えないといけないという気になっていったというのはあります。
話を戻すと、コンピューターで出力する技術はすぐに日本にも入ってきて、新しいデザイン会社とかが流れ始めていました。でも、伊東屋には使える人がいない。だから、社員でメンバーを募って、勉強会を開いたり、講習会に行ったりしていました。そこで僕が旗を振ってましたね。平成4年頃でしょうか。
――社長になることは、どの段階で腹に決めたのですか
伊藤 90年代後半、僕がPOSレジ(販売実績などをデータ管理できるレジ)の導入を進めていた頃のことです。
叔父も専務も、レジ打ちはスピードが遅くなるからやめた方がいいって言ってるような状況でした。でもある日、祖父が僕に「お前今何の仕事してる」って聞くから、POSレジ導入をしていると。祖父はすぐに理解できず、困ったなと思っていたら、横にいた叔父が全部説明してくれました。
今まで反対してて、何の話も聞いてないと思っていた叔父が、僕の仕事を全部把握し、祖父を納得させる。すごく感動しました。
――叔父さんは分かってくれていたのですね。
伊藤 そうです。それから本当に2、3日後、祖父が亡くなりました。葬式の席で、叔父が「調子が悪いから僕の後ろに立っててくれ。倒れそうだったら支えてくれ」と言うんですね。色んな意味を込めて言っていたと思います。
その後、ニューヨークで見本市があり、叔父が「調子が悪いからお前代わりに行け」と。大喜びでアメリカに行って、帰ってきたら叔父が大動脈瘤破裂で入院していました。その場で死んでもおかしくなかったらしいです。
不幸中の幸いは、叔父は太っていたので、体重で動脈が押されて大量出血しなかった。叔父は一命をとりとめましたが、「後はお前がやるんだ。しっかりしろ」と話をされました。だから、叔父が倒れた時に「社長」を一番意識しましたよね。
――2005年に社長に就任されるまでは、まだ少しありますね。
伊藤 叔父は、手術して良くなりそうだったのですが、再び意識を失い、1年近く意識が無い状態が続きました。その頃、会社のコントロールは専務に移りました。
伊東屋は、2004年が創業100周年だったんです。記念事業の準備をするグループがありましたが、僕は入れてもらえませんでした。記念パーティーでは紹介こそされ「跡を継ぎます」って話は何もない。
でも、10月の株主総会の1カ月前、叔父から社長室に呼ばれて、「10月の株主総会で社長に指名するから、社長やりなさい」といきなり言われました。
社長就任、VS専務 「柵の中の羊」を走らせるには
――専務が実権を握っている会社で、メーン事業から外された人が社長になる。混乱しませんでしたか。
伊藤 小さな会社だから、みんな僕が社長になることは知っていました。株式の保有も問題なかったです。ただ、専務は僕をコントロールできると思っていたはずです。
――でも伊東社長は、実権を握らせるつもりはなかった。
伊藤 はい。専務は高齢でしたので、相談役を打診して役員は下りてもらった。まだ、彼の息のかかった人たちがいっぱいいたんで、当時の取締役や部長にプレゼンをしました。
2枚の絵を描いて、片方は柵の中に羊が放牧されていて、自由な方向を向いている。「これが今の伊東屋です。あなたたちは専務の枠から全く出ようとしないが、好き勝手にやっている」と。
もう1枚は、丘の上を羊が並んで歩いてて、一つの星に向かっている。「あなたたちのことを縛るつもりはないが、同じ方向を向いてほしい」と訴えました。
――プレゼンを聞いていた取締役の人たちは専務派ですか。
伊藤 だいたいそうですよね。あんまりちゃんと聞いてなかったと思いますが。専務のプレッシャーから解放されたけど、専務がいつ戻ってくるか分かりませんでした。あと、僕も「羊を囲む柵」を立てるだろうなと思ってた人は多くいたんじゃないかな。
――専務の力を利用して、社長業を進めることもできたと思いますが、その選択肢は採らなかったのですか。
伊藤 店がちっとも面白くなくて、お客さんが来ない。もう変えなきゃしょうがないなと思っていました。もう一つ、気持ちが悪かったのですが、当時の役員たちがバタバタ死んだんです。
本当にびっくりするぐらい、年に1人2人と亡くなりました。みんな団塊の世代で、多分本当に休みをもらえずにずっと働いてきた人たちでした。結果、専務派の立場が弱くなったと思います。殺してないですよ。念のため。
――もちろんですよね。一つの星を目指す社内の空気を、どのように醸成されたのでしょうか。
伊藤 どうですかね。年功序列で役職に就ける仕組みから、目指す組織像を提示し、そのための部長を任命するように変えました。現実には仕事ができない人も多く、部長の肩書を1回外さないといけない人も多かったですけどね。
また、組織風土を変えるという意味では、中途の若い女性たち。ある程度経験を持った人が、伊東屋の良い面だけを見て何か入ってきてくれた。
たとえば、若い女性の社員で、百貨店で内装をやってた人材がいて、内装を変え始めました。内装を変えると、売れ筋が変わるんですよ。新しい空気が入ってきて、少しずつ会社が変わってきたなと感じるようになりました。
ゼネコンに「カチン」 老舗ブランドの看板を守る
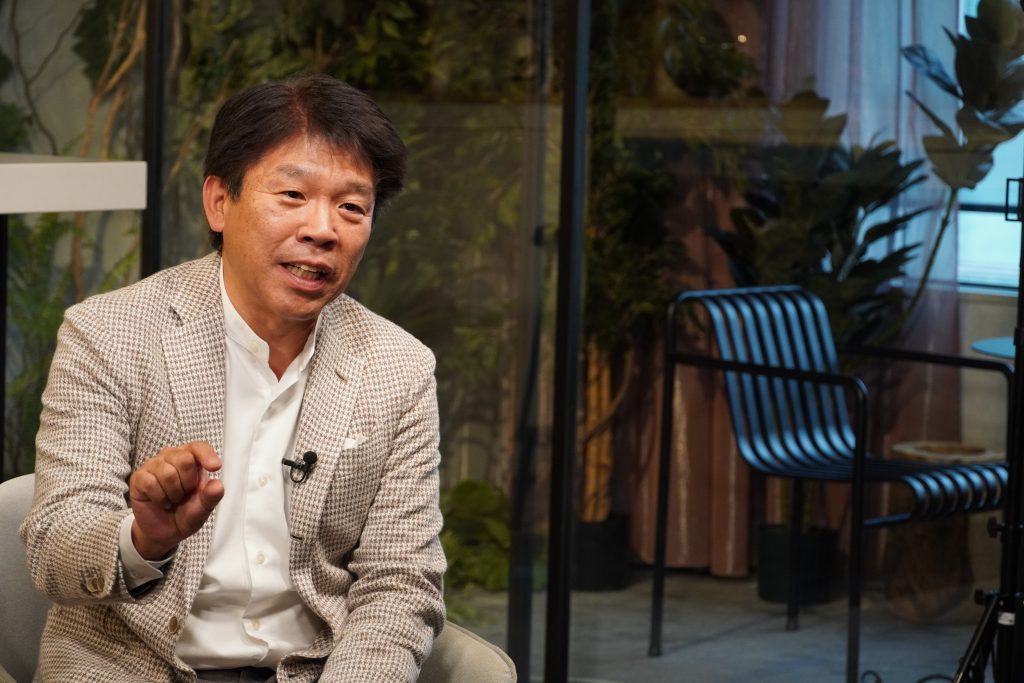
――組織風土を変えつつ、老舗ブランドの看板も守っています。
伊藤 その頃、本店の建て替えをしようという話になり、ある大手ゼネコンの営業が「伊東屋は将来儲からないから、店を閉めて貸しビルにしましょう」と提案してきました。100年続く誇りある仕事を、ゼネコンの営業1人が「無駄な商売やめろ」と言うわけです。
カチンときましたけど、すごく本音を聞いた感じがしました。「伊東屋がいいね」という声の裏にも、銀座で不動産業やった方がいいという本音が潜んでいるかもしれない。
そこで、新しい本店が建った時、お客さんをがっかりさせないため、社内や顧客、取引先に「どういう伊東屋になったらいいと思うか」というインタビューを2年かけてやりました。
――どんな答えが。
伊藤 それが、出てくる答えは全部「伊東屋は伊東屋でいい」。みんな、格好良い答えを出したつもりなんですけど、こちらはさらに混乱する。
そこで、2、3年目の社員に裁量を与え、プロジェクトのマネジメントを任せ、伊東屋らしさをまとめました。「好奇心を持って新しいことをやる」「使い捨てではなく、自分の子に引き継げる商品」とか、一つずつ挙げていく。「目指す星」がはっきり見えるように。
すると、今まで大人しかった若い社員がガーッと出てきて、自分からどんどん新しいものを作るようになりました。やっぱり自由にさせないと人は動かないなと思いました。
――事業承継された時の社内風土を変えたスタンスが結実しましたか。
伊藤 そうですね。多分、前の専務のように「柵を作る」と思っていた人たちからも信頼を得られた気がします。自分のことを理解してもらうのにすごく時間はかかりました。
理解してもらう過程では、ずっと背中を見られてるわけで、そこに一番気を使います。もちろん怒ることはありますよ。でも、理不尽な怒りは絶対見せちゃいけない。自分で正しいと思っても、間違いだと気づいたときに、いかにブレーキを踏めるか。そんな事が何回かありました。
――次世代への事業承継も考えておられますか
伊藤 うちの息子と娘がいるんですね。専門分野が違うから、2人はバッティングせずに経営に参加できる。日本では、事業承継をすると、次の人が1人で背負うイメージが強いですが、イタリアのファミリービジネスだと結構家族で動いている。
姉はマーケティングに強く、弟は数字に強い。妹はテクノロジーに強いとか。組織化されたファミリービジネスの勉強を子供にさせたいと思っています。会社を継げと言ってはいませんが、やる気はあるみたいなので。
記事本編とは異なる特別インタビュー動画をご覧いただけます
SHARE
記事一覧ページへ戻る