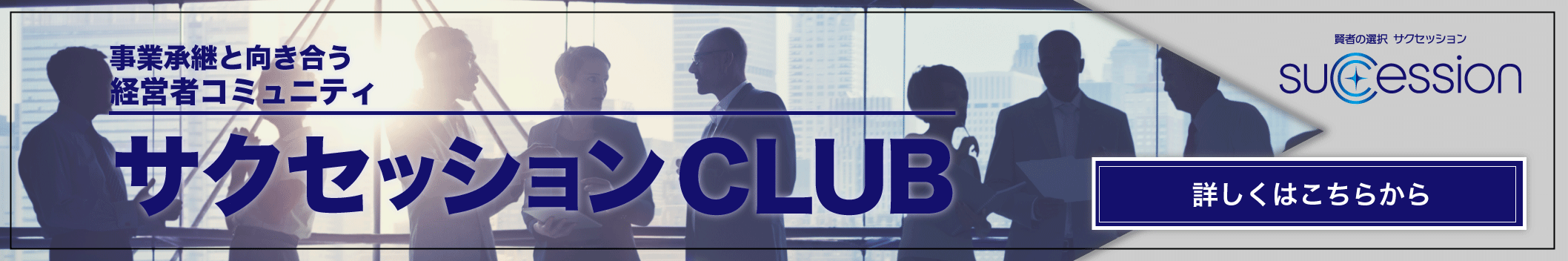COLUMNコラム
「化石か!」帳簿は手計算でIT化ゼロ カリスマ社長が65年君臨「イエスマン」の社風を変えた3代目~山櫻【前編】

65年間、豪腕のカリスマ創業者が君臨した会社は、「イエスマン」しか育っていなかった。組織風土が硬直化していた創業92年の紙製品メーカー「山櫻」を、創業者の孫にあたる現社長が継いだのは20年前のこと。その後、乗り遅れていたデジタル化を推進し、会社にチャレンジできる社風を根付かせ、社員を100人以上増やした。どのような事業承継があったのか、市瀬豊和社長に聞いた。
目次
戦争帰りのカリスマ創業者、91歳まで社長
――創業者の祖父・邦一氏は相当なカリスマだと。どんな方だったのですか。
市瀬 創業者って、会社が自分の体の一部なんですね。2代目3代目とは大きく違って、なかなか譲れないから、亡くなるまで社長を続けていました。
周りの社員は相当大変だったと聞いてます。呼びつけられて、1時間半立たされて貧血になる社員もいたそうです。
とはいえ、人格は非常に真面目。戦争に行って弾が2発貫通して死にかけた人間ですから。恐怖政治というよりは、社員が創業者のカリスマ性に付いていく社風だったのでしょう。
――祖父の邦一氏は、経営手腕も秀でていたのですか。
市瀬 紙製品の業態は、高度経済成長を経ても大きく変わらなかったんです。昭和50年代、オイルショック後は倍々ゲームに数字が伸びたって言ってました。そういう意味では、91歳の社長でも何とか回せたのかな。もちろん、右腕左腕の番頭さんがいて、サポートしてきたからこそですけど。
ピークの売り上げは140億、私が社長になって、1年目か2年目くらいのことです。
お年玉もらうときには「会社を手伝いなさい」

――市瀬社長が、事業承継を決めたのはいつのことでしょうか。
市瀬 祖父は娘が2人おり、私の父と叔父は養子縁組でした。父と叔父とも2人ずつ子がおり、祖父からすると私も含め孫が4人いました。
幼稚園か小学校低学年の頃ですけど、お年玉をもらうときに4人呼ばれて正座させられて、「お前たちは大きくなったら山櫻を手伝いなさい」って。ある意味洗脳されてきましたね。
小学6年の作文には、「祖父の会社を手伝う決心」って題名で作文を書いているので、既に意識をしていたわけです。
――大学卒業後、山櫻にすぐ入られたのでしょうか。
市瀬 小学5年からずっとラグビーをやってたんです。その間は、ほぼ会社のことは忘れて、慶応大でラグビーのみに打ち込んでいまして。日本代表に手がかかるところまで行きました。
就職活動で、サントリーと第一勧業銀行(現・みずほ銀行)に誘われました。ラグビーでサントリーに行く選択肢もあったけど、将来の会社経営を考え、山櫻のメインバンクの第一勧銀に入りました。
銀行勤め、祖父が勝手に「辞めさせる」
――その後、山櫻に入られた経緯は
市瀬 海外を知りたくて留学を目指していたのですがね。祖父が、私の知らないうちに第一勧銀に来て、「そろそろ孫を辞めさせる」って言っちゃったんですよね。銀行内で大騒ぎになりました。
また、第一勧銀にいた時に結婚を決めていたので、やめる前に、英語の勉強と社会勉強と新婚旅行等を兼ねて、夫婦でニューヨークに1年間行きました。
そして、29歳で山櫻に入りました。まだ、祖父が80代で社長をしていましたね。
――入社した頃の社風は、どうでしたか。
市瀬 とにかく社長が怖いので、みんな社長にひれ伏すというか、触らぬ神に祟りなしというか。社長に怒られないように仕事をする、ある意味真面目な社員が大半でした。それ故に、チャレンジしづらい環境、組織でした。
ファミリー企業ってだいたいそうですが、創業者の社長に逆らって、社長の意見を変えてまでチャレンジするってなかなか難しいですね。
「化石か!」平成の世にIT化ゼロ
――社風以外に衝撃を受けた点がありましたか。
市瀬 入社後、工場で半年研修した後、挨拶回りをしたり、営業をしたりして、山櫻の業務全体を学んだんです。そこで、「この会社はまずいな」と思ったのは、もちろんワンマン社長のこともあるんですけど、もう一つIT化が全くされていなかったんです。
1990年代前半ですが、当たり前に経理や給与計算、在庫管理は、電子化されている時代でした。でも、うちの会社はほぼゼロだったんですよ。
給与計算は、社員2人ぐらいが、部屋にこもって現金を集めて、それで配ったりしてたんです。そういう時代です。商品も3千点ぐらいあるんですけど、在庫管理は全部帳簿ですから。足し算引き算してね。これを見たときは、本当に「化石か!」って。そこが一番ショックでした。
だから、営業時代から、社内全体のIT化を進めたのが一番の仕事でした。会社全体のお金や商品の流れが全部理解できますから。その意味では、社長になるときに非常にためになったと思います。
このままでは会社に未来はない、印刷業界もやばい

――1997年に、祖父の邦一氏が亡くなられ、叔父さんが2代目として社長を継がれました。
市瀬 祖父が亡くなり、叔父が社長になったんですね。ただ、社員の感覚からいうと、正直あまり変わっていなかったと思います。何となく、オーナーに逆らったら辞めさせられてしまうんじゃないかとか、異動させられてしまうんじゃないかとか。
実際にそういう噂もありましたし、人間って弱い生き物ですから「触らぬ神に祟り無し」という風土は変わりませんでした。その考え方の改革が一番ですね。今でも僕としては大変です。
――社長になる前から、社風変革に取り組まれていた。
市瀬 他の人は、なかなか難しいですよね。言われたことをやってくれば良かった社風ですから。同族企業にありがちな話だと思います。私は、このままだったら会社の未来はないっていう気持ちで仕事してました。
IT化ともう一つ、やっぱり紙製品だけではまずいなと。Macとか出てきて、今までは印刷機で名刺を作っていたのに、パソコンとプリンターで名刺を作る時代が来た。印刷業界やばいなと。
それで、ある会社をM&Aしたんですけど。まだ、祖父は存命で、喧嘩をしながらもお金を出してもらった。祖父からするとM&A自体、あまり認識がないんですよ。だから、そんな『空』なものに金出してどうすんだって怒られて、祖父とは2回ほどやり合ったんです。
祖父はケンカすると、目の色が変わるんですよ。「お前は若造のくせに、屁理屈こねやがって」みたいに、グレーに変わるんですよ。目の色が(笑)。
新社長は41歳、年上役員に気を遣いつつ
――社長に就任したいきさつを教えてください。
市瀬 41歳、入社して12年目ですね。まだ若かったですが、会社の風土やデジタルの遅れも含め、このままだと本当にまずいなという状況でした。叔父と父親に、もし僕に譲る前提があるならば、なるべく早くとお願いしました。役員も早い方が良いという合意もありました。
――他に兄弟やいとこがいる中、スムーズに決まったのでしょうか。
市瀬 それは非常に簡単で、直系長男。直系の男1号だからですよね。長女の長男ですから。後から聞いた話では、祖父は自分がもうちょっと頑張って、直接孫に譲りたかったと言っていたそうです。
――カリスマ創業者の作った風土が残る会社で、社長に就任する時、最も意識したこと、神経を使ったことは何でしょうか。
市瀬 やはり、私が社長になった時、私の親の年代の役員ばかりでしたから、役員会も平均年齢70歳。言葉を選びながら、父親の年齢のような役員を説得して会社を変えていくので、すごく神経を使ったし、体力を消耗しました。言葉もタイミングも選ぶ感じですね。
一方で、社長に物を申せないっていう伝統は変えないといけない。直接私に何か言って反対する人は、そういない。でも、私は社長に物を申してこれ違うって言ってくれる人を信じるようにしました。
――組織風土を変えるために、具体的に心がけたことは何ですか。
市瀬 一番は、会議で自分が喋るのをなるべくやめました。最初のうちは私も体育会系で、怒ったりしていたんですけど。でも、「これをやると元の木阿弥だ」と思い直して、胃がキリキリしながらも、聞く時間を増やしました。社員が会議で発言しないのなら、本当に普段、自分の仕事のことを考えているのか疑問ですよね。
社長になって20年近く経ち、部長職は全員年下になりました。だいぶ社内風土は変化したんじゃないでしょうか。
山櫻…1931年に「市瀬商店」として、市瀬邦一氏が26歳で創業した。名刺やはがき、封筒などの紙製品の製造・販売を手がける。邦一氏は、1997年に91歳で亡くなるまで社長を務めた。その後、邦一氏の次女の夫が2代目社長となり、2004年から市瀬豊和氏が代表取締役社長。年商119億円(2023年2月期)、社員数は507人。本社は東京都中央区。
※こちらの記事は追記・修正をし、2024年3月28日に再度公開しました。
SHARE
記事一覧ページへ戻る