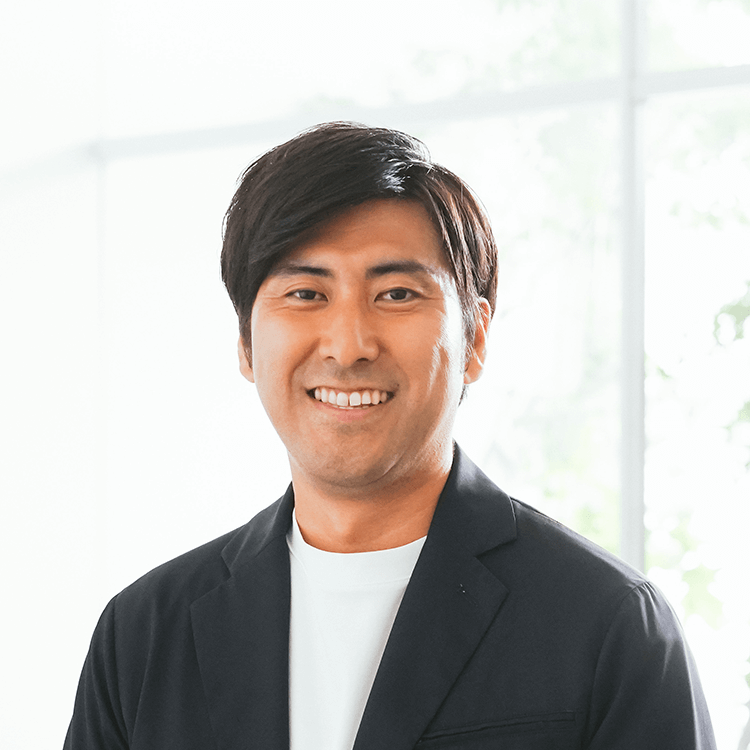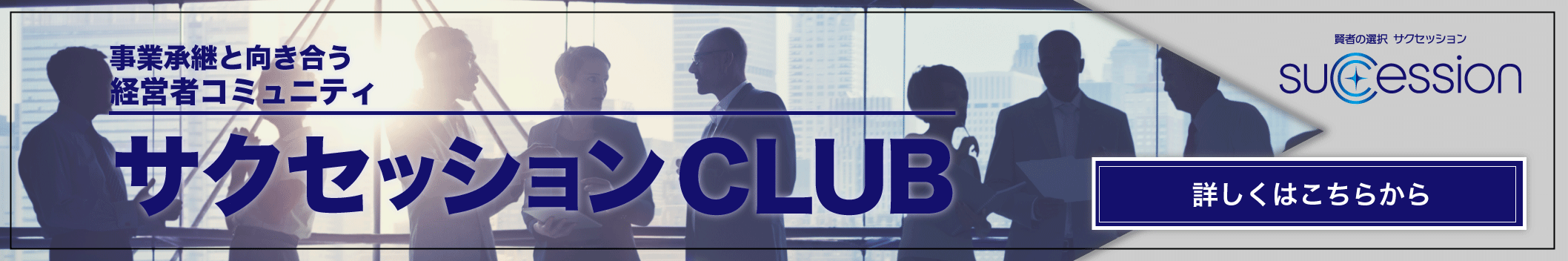COLUMNコラム
メジャーリーグを目指した日本人投手、34歳で投資会社社長に ドラフトかからず、ビジネスで世界に挑む

ストライダーズ(東京都港区、東証スタンダード市場)は、不動産事業やホテル事業、海外事業に投資し、経営管理する投資会社だ。早川良太郎社長は、大リーガーを目指してアメリカの大学で投手として活躍し、全米大会にも出場した異色の経歴を持つ。2018年に34歳の若さで、前社長の父・良一氏から上場企業を事業承継した経緯を聞いた。
目次
「お前に任せるよ」
——ストライダーズの社長に34歳で就任されました。上場企業としては随分早い社長就任ですが、どんな受け止めでしたか。
早川 漠然とした不安や怖さがありました。しかし、私の同世代にも起業したり、事業承継したりして、会社を経営している仲間が何人かいました。彼らをみていると、社長になるのは早い遅いではなく、タイミングが大事だと思いました。
父の打診から半年ぐらい考えましたが、「お前に任せるよ」と言われたのが受け継ぐタイミングと思い、引き受けました。
——ストライダーズは上場企業ですから、社長交代が正式に決定した後は株主総会を含めて株主には丁寧な説明が必要ですが、反対意見などはなかったのですか。
早川 幸い、「社長が代わるのなら応援するよ」という声を株主の皆様からいただき、すごく背中を押してもらいました。当時、個人株主の所有割合が7割程度でしたが、反対意見は聞こえてきませんでした。
——上場企業を親から子に承継されたことで、「社会的にどう受け止められるだろうか」という不安はなかったでしょうか。
早川 反対意見は出ませんでしたが、当然、上場会社は公器ですから、説明責任がとても大切です。IR活動やPR活動で、自分が今、何を考えているのか、何をしようとしているのかを丁寧に伝える場を作らねばならないと考えていました。不安というよりも一つのチャレンジだと、ポジティブに受け止めました。
「大魔神」に憧れた高校球児、アメリカへ

——学生時代、米国に野球留学し、その後、オリックスで6年間、ビジネスマンとして働かれました。なぜ野球留学をされたのですか。
早川 千葉県の成田高校で高校球児として甲子園を目指していました。高3の時、千葉県大会のベスト16で負けてしまい、日本の大学で野球を続けるか、米国に行くかを迷いました。
ちょうど、メジャーリーグでイチローさんや「大魔神」佐々木主浩さんが、シアトルマリナーズで大活躍されていました。その試合をアメリカに見に行ったのです。佐々木さんが9回に登板し、ビシッと3人で抑えました。
スタンディングオベーションで日本人が称賛される姿を見て鳥肌が立ちました。私もいつか同じような瞬間を味わいたいと思い、アメリカで野球を続けることを決断したのです。
——現地の英語学校に1年間通い、翌年にカンザス大学に入学されました。大学では野球漬けですか?
早川 野球ばかりではありません。アメリカの大学は、学業の点数が悪い場合は試合に出場できません。
私の場合、英語力がまだ十分でなかったので、練習後に家庭教師と一緒に勉学をして、単位を取りました。文武両道で野球と勉強を両立させるところがアメリカの大学のいいところです。

——野球の成績はどうだったのですか。
早川 私の大学は、中西部の大学が集まるビック12というリーグに所属し、3年の時にリーグ優勝し、全米大会に出場しました。
私は中継ぎ投手でした。ピンチの場面や2対1で勝っている試合の8回といった緊迫した場面に、「良太郎、行ってこい」と言われ、マウンドに何度も上がりました。
——そのまま大リーグに行きたいとは思いませんでしたか。
早川 チームメートには大リーグに行くメンバーがたくさんいました。でも私はドラフトにかかりませんでしたから、次の道はありませんでした。メジャーリーガーになった仲間を目の前で見ていたので、自分はここまでのレベルだなと、野球をきっぱり諦めました。
専攻は経済学だったので、いったん日本に帰って、仕事を学び、将来アメリカで仕事をしようと、当時は考えていました。
そして、オリックスへ

——その後、帰国してどうしたのですか。
早川 卒業した夏、留学生向けのキャリアフォーラムが東京・有楽町であり、オリックスの面接を受けました。父が銀行員だったので金融関係がいいのではないかと思ったことと、オリックスがプロ野球球団を持っていたことが決め手でした。面接はとんとん拍子で進み、受かりました。野球のお陰かもしれません(笑)。
——オリックスで6年間、どのような仕事をしたのですか。
早川 リーマンショックがあった2008年に入社し、2年目に法人営業からエコプロダクトチームという環境ビジネスの部署に配属されました。オリックスがファイナンスから事業にシフトしようとしていた時期です。
そこで私は水をテーマにビジネスを立ち上げるという特命チームに加わりました。
——どんなプロジェクトに取り組んだのですか。
早川 一つは上下水道事業です。地方自治体の予算が縮小される中、インフラが老朽化していることが問題になっていました。それをオーバーホールするために、オリックスが提供できるファイナンス・サービスはないかと国内外の事例を調査・研究しました。
またペットボトルのパッカー事業をしている会社とタイアップし、オリックスによる水のペットボトルの商品化も検討しました。世界には「水メジャー」といわれる会社があるのですが、どうやったら日本企業が対抗できるかを検討しました。
チームでは最年少だったので、雑用係も含めて先輩社員をどう巻きこんでいくか学び、役員会の資料準備などを経験しました。最後の2年間は神戸支店に配属となり、中小企業から上場企業まで営業を担当しました。オリックスの6年間で本部チーム、支店チームと属性が違う組織で働き、営業スタイルも違う仕事をしましたので、多彩なビジネス経験を積めたと思います。
海外でのチャレンジ求め、ストライダーズへ

——その後、2014年に父親が社長を務める事業投資会社のストライダーズに入社します。どういう経緯だったのでしょうか。
早川 オリックスで6年間お世話になり、今後は海外でチャレンジしたいと考えていました。そんな考えを父に伝えると「ストライダーズはこれから海外事業を伸ばしていきたい。ジョインする気があるか」と言ったのです。
ちょうど30歳を迎え、一つの転機ではないかという思いもあり、ストライダーズに入社をすることになりました。
——父親が経営する会社に入ることに躊躇はありませんでしたか。
早川 正直迷いはありました。父と一緒に仕事をやっていけるのだろうかという漠然とした不安もありました。一方で、大きなチャンスではないかとも 思いました。父が海外で色々と経験してきたことは知っていました。一緒になって会社を大きくすることができるのであれば、トライしてみようと決断したのです。
(文・構成/安井孝之)
記事本編とは異なる特別インタビュー動画をご覧いただけます
SHARE
記事一覧ページへ戻る