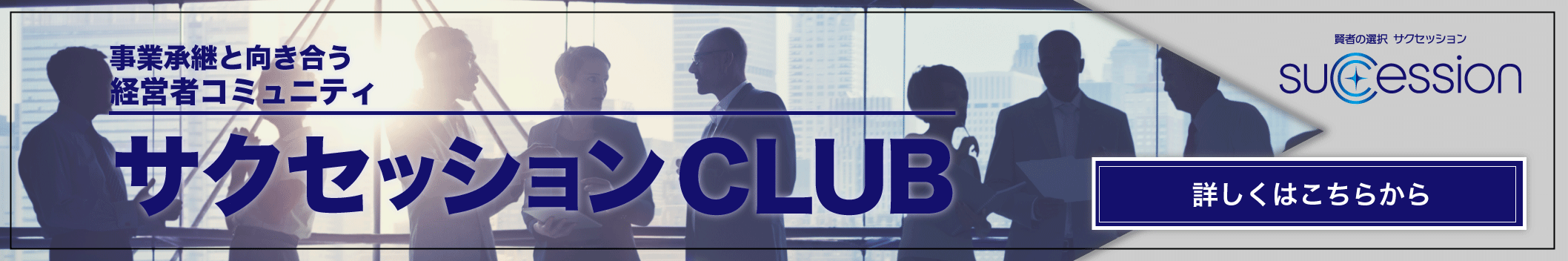COLUMNコラム
相続税対策だけじゃない! 「生前贈与」で事業承継を行なう3つのメリット

生前贈与というと相続税対策をイメージする人も多いと思いますが、事業承継のときにも株式の承継など幅広く活用されています。本記事では、生前贈与のメリットとデメリットを解説します。
目次
生前贈与とは?
生前贈与とは、贈与する側と受け取る側の双方が合意のうえ、個人が自分の財産をほかの誰かに贈与すること。事業承継の文脈では、経営者が存命中に自社株を後継者に贈与することを意味します。
生前贈与の大きな目的は、財産それ自体を減らすことです。通常、贈与という行為においては贈与税が発生する余地があるわけですが、生前贈与には暦年贈与と相続時精算課税制度があり、これらを活用することで贈与税は非課税になります。
暦年贈与
生前贈与でも最もメジャーなのが、暦年課税制度。通称、暦年贈与と呼ばれます。いわゆる、年間110万円以内の贈与なら、贈与税が非課税になるという制度です。
暦年贈与なら贈与者や受贈者の制限はありませんし、届け出を提出する必要もありません。年間110万円以下、最大で2500万円まで贈与税が非課税になります。110万円ずつであっても、数年、十数年かければまとまった金額を贈与できるでしょう。
相続時精算課税制度
これは、60歳以上の贈与者が20歳以上の子または孫に対して、2500万円までの生前贈与をまとめて非課税にするが、贈与した人が亡くなったときは贈与した財産分も合わせて相続税を納税するという制度です。暦年課税が毎年110万円以下まで非課税にするなら、相続時精算課税制度は2500万円分の非課税の範囲をあらかじめとっておくイメージです。
たとえば、3000万円の資産を持つAさんが、相続時精算課税制度を利用して息子に2500万円贈与したとします。2500万円までは非課税なので、贈与税はゼロです。したがって、Aさんの資産は500万円になり、2500万円はそのまま息子の手元に移ることになります。しかし、Aさんが亡くなったとき、相続税は手元資金の500万円ではなく、相続時精算課税制度を利用して贈与した財産の2500万円を足した3000万円に対して発生します。
また、相続時精算課税制度には届出の提出が必要であり、一度選択すると永久に継続されるといったデメリットもあります。さらに、暦年贈与と相続時精算課税制度は、どちらかしか利用できません。
事業承継における生前贈与の3つのメリット
①後継者が早期に経営に参画できる
後継者は、遺言なら現経営者が亡くなるまで、売買なら契約を交わすまで、自分が会社を承継するのだという確信を持てずにいます。なぜなら、現経営者から直前になって「やはり君に事業は任せられない」といわれるリスクがあるからです。
ところが、生前贈与であれば、贈与した時点で自社株の権利が後継者に移転しますし、後継者に対して名目上のみならず法的にも経営権を譲ることができます。そのため、後継者の経営に対する意識を高められますし、後継者も安心して事業承継を引き受けることが可能です。
②遺留分侵害額請求への対策になる
遺留分とは、相続が発生したとき、配偶者・子ども・直系尊属(親、祖父母など)に与えられた最低限保障された取り分のこと。たとえば遺言書に、私の全財産は愛人に相続させると書いてあったとしても、残された妻や子どもも財産の一部を受け取ることができます。
一部の相続人だけが相続・贈与によって多くの財産を取得した結果、遺留分をもらえなくなった相続人が、相続・贈与を受けた人に対して遺留分の補填額を請求する行為を遺留分侵害額請求といいます。また、遺留分侵害額請求権が行使された場合、後継者は他の相続人に対して一定額を支払う必要があります。
しかし遺留分があるのは相続開始前10年間であるため、早いうちから生前贈与をしていれば、後継者が他の相続人から遺留分侵害額請求権を行使されるリスクはなくなる、もしくは行使されたとしても支払う金額が減る可能性が高まります。
③後継者が自社株を取得する対価を必要としない
売買によって従業員に事業承継する場合、後継者は自社株を買い取るための資金を用意しなければなりません。しかし、往々にして莫大な資金が必要になることも多く、後継者が買取資金が出せないという理由で事業承継を断るケースも珍しくありません。
一方、生前贈与であれば、売買ではないので取得対価という概念がそもそもありません。つまり、後継者は自社株の買取資金ゼロで事業承継できるのです。もちろん生前贈与だと贈与税は発生しますが、前述した暦年贈与、もしくは相続時精算課税制度を活用すれば、贈与税の負担を小さくすることができます。
まとめ
生前贈与は、節税や後継者のモチベーション向上といったメリットがあり、事業承継においても有効な手法といえます。しかし、生前贈与の恩恵をより多く受けるためには、少しでも早い段階から取り組む必要があります。専門家の助言のもと、少しでも早めに行動するよう心がけましょう。
SHARE
記事一覧ページへ戻る