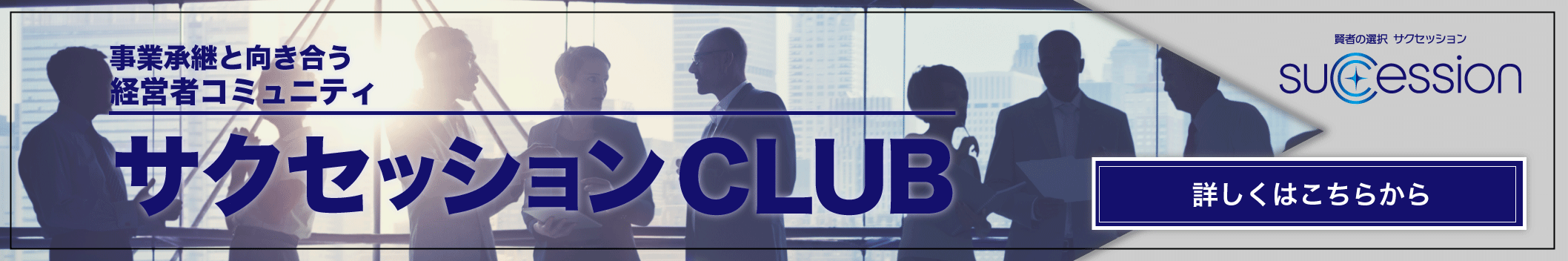COLUMNコラム
「品女って分かるとバカにされるから、帰り道で制服を着替えた」 廃校危機から志願者30倍、偏差値も急上昇 品川女子学院の奇跡

1925(大正15)年創立の女子校、品川女子学院(東京都品川区)。来年で創立100年を迎える伝統校ですが、1980年代は不人気で廃校の危機を迎え、生徒が「制服を着ているとバカにされる」と嘆くほどでした。しかし、創業者のひ孫で、現理事長の漆紫穂子さんが、制服刷新や中高一貫化などを進めて志願者を急増させ、人気校に復活させました。「品女」の奇跡の成功と復活への歩みを、漆さんに聞きました。
目次
作詞は与謝野晶子、曾祖母が創設した伝統の私学
――品川女子学院の校歌に「バラの花は香る。ましてここに学べる少女(おとめ)」という歌詞があります。格式高い歌詞ですが、作詞が与謝野晶子さんなんですね。
漆 そうです。戦前と戦後で校歌を変えざるをえない学校が結構あった中、品川女子学院はそのままずっと使っています。戦前の歌詞ですが、平和というキーワードもあります。女性だからこそ、平和の使いであるっていうような歌詞なんです。
私の祖父が作詞のお願いに行くと、たまたま与謝野さんのご長男とうちの祖父が同じ名前だったんですよ。そんなご縁もあり、作詞を受けていただいたそうです。
――品川女子学院について教えてください。
漆 創立が1925年で、まもなく100年を迎えます。創立の数年前、私の曾祖母が手に職をつける女性の集まりを作ろうとしました。当時は、参政権が女性にない時代でした。
当時、参政権運動に注力する女性もいましたが、曾祖母は次世代に種まきをしたいと考え、サークル活動みたいに始めたんです。その2年後に関東大震災が起きました。
復興が進む中、最初の校舎に使う木材やミシンなどを皆さんから頂き、さらに私財を投げ打つ形で作ったのが品川女子学院です。苦しいときも、こうした歴史が支えになってきました。
戦争直後の集合写真をみると、服装がバラバラなんですね。男性の服を着ている子もいれば、セーターやセーラー服もいるし、人も少ないんです。こんなに物資がないときも、学校の灯火を消さなかったんだなって思うと、苦しいときも絶対に繋がないといけないと思います。
学校一家に生まれ、国語教師に

――創立者のひ孫にあたる漆さんは、校長先生としては何代目ですか?
漆 校長としては6代目です。創業家ではない方がやっていた時期もありましたので、漆家としては4代目です。
――幼い頃は、どんな子どもだったんですか?
漆 外では優等生だったと思います。子どもの頃は体が弱かったんです。母が心配して連れて行った水泳教室がきっかけで丈夫になり、今も年齢別トライアスロン日本代表です。今日も2キロ泳いできました。
子どもの頃は、祖父が理事長・校長で父と母が手伝っていました。母は、授業を持ちながら経理も兼任。父も授業を持ち、家では生徒の楽しい話題もよく出ていました。一方で、経営が苦しく地獄みたいなことも見てきましたね。
――将来、両親の後を継ぐかもしれないという意識はあったんですか?
漆 「あるのかもしれないな」という一方、あまりに大変そうなのと、両親が「子どもは二の次」という感じだったので反抗心もありました。忙しいときは、帰ってくるのが午前3時のこともあり、継ぐのは嫌でしたね。
一方で、教員としての両親は尊敬していました。教員にはなりたいけど、経営者にはなりたくない。生徒のことだけでなく、「お金がない」「もめ事をどう処理する」などの話題も聞いていたので、1番なりたくない職業が経営者でした。
――早稲田大学に入り、国語教師を目指していた。
漆 徹底的に勉強し、教員資格を取りました。でも、最初は純粋に教師になりたく、「経営」を避けるために、品川女子学院には勤めず、別の私立中高一貫校に入りました。そこは本当に楽しかったです。担任も持たせてもらい、学校が天職だなって思いました。
女子校で中学生を受け持ったのですが、本当にわがままな子がおり、みんなとの揉め事を通して成長するんです。毎日子どもに変化があって、泣いちゃうぐらいのことがあるんです。毎日泣いちゃう仕事なんて、そんなにないんじゃないかなって。毎日感動しながら働きました。
人生の転機、28歳の決断
――1989年、28歳で急に品川女子学院に戻られています。
漆 はっきり言うと、倒産危機です。当時の品川女子学院は、人気がない5本の指に入っていました。また、母が卵巣癌の末期で余命半年って言われました。
このまま品川女子学院がつぶれたときに、私幸せかなと思ったんですよ。それで、決断をしました。
継いでほしいとは一切言われませんでした。ただ、かつて祖父だけが「お爺ちゃんが頑張ってやってきた、ママやパパが守ってきた学校を次はお前にやってほしい」と言ったんですよ。それは心に残っていました。
――戻った当初の状況はどうだったのでしょう。「後継者が帰ってきた」みたいな感じで受け取られたのでしょうか。
漆 そういう受け止めは、多かったと思いますね。先生たちはみんな善意で一生懸命やっていたんですよ。でも、私が戻った前後、中等部の入学者が5人という時代がありました。このままでは潰れるなと思いました。
当時、私立校の世田谷学園に山本慈訓先生という名物校長がいて、学校改革して文武両道で伸ばしていました。話を聞きに行くと、最初に「あなたの学校は潰れないから大丈夫。今できることあるでしょ」と言われました。
――どんなことに取り組まれたのでしょうか。
漆 私は、公立と差別化するためには中高一貫校しかないと思っていました。でも、当時の品女は、高校募集のレベルアップに傾注し、中等部の充実は頭になく、塾回りをして小学生のための説明会を開くということに理解が得にくかったんです。
当時、授業を持ちつつ副担任を務め、広報部がないから一人で広報部をやって。激務で疲労困憊し、家に帰ると手が震えて鍵穴に鍵が入らないときもありました。もう本当にやるか死ぬかという感じでした。
そんなとき、母が亡くなりました。あと半年と言われたのに、母は余命半年と言われながら、「5号館の新築までは生きます」って宣言して、本当に5年ぴったり生きたんです。うちの学校は守るべきものだと強く感じるようになりました。
「制服変えてよ…」悲しく響いた生徒の声
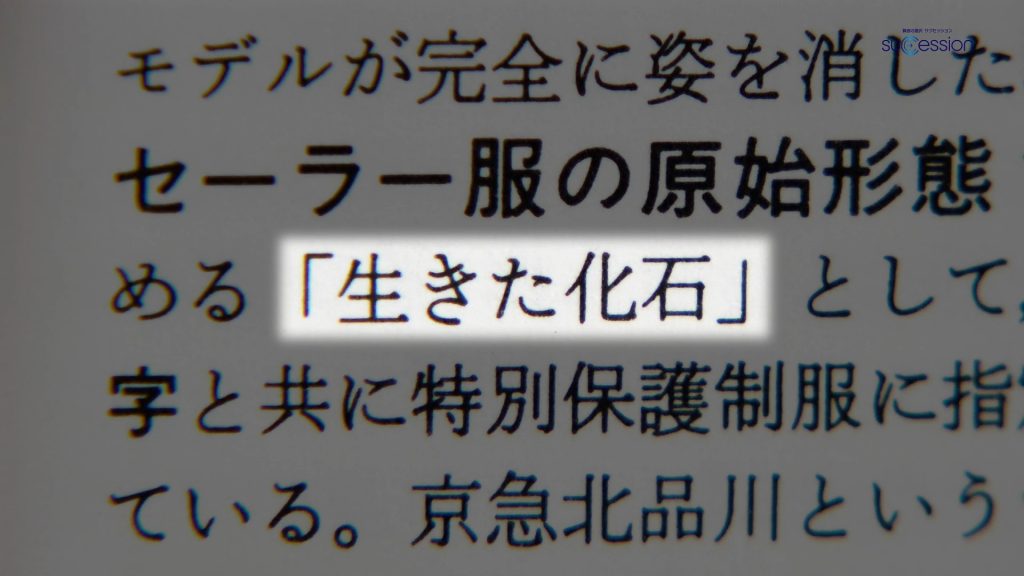
――制服を替えるきっかけがあったのでしょうか。
漆 当時、私は子どもと近かったから生徒にもいろいろ言われました。ある日、「先生、校長の娘でしょ。制服変えてよ」と言われました。
当時、品女という言葉は、差別的なニュアンスで使われていました。「品女って分かるとバカにされるから…」と、帰り道で着替えた子がいたことを知り、それがすごく悲しくて。
せめて制服ぐらい毎日着るから、人に自慢できるものを作りたい。生徒が、親や友達に自慢できるものを何か作りたいと言うので、自分たちでデザインして制服を変えました。
――さらにPRにも取り組まれたと。
漆 当時、「女子高生制服図鑑」という本に、品女の制服は「生きた化石」と書かれていました。制服を替えたことを知らせたいと思い、「女子高生制服図鑑」の出版社に送ったんです。
すると、結構取材が来るようになりました。生徒が、学校のことがニュースになって家で自慢したとか、何でもいいので、自慢できることをとにかく作りたかったのです。
一方で、経営者になって教育の心を忘れたとか、結構言われました。痛かったですね。もともと教員になりたかったから、経営者になりたくない人だったから。
そのとき、祖父の「心頭滅却すれば火もまた涼し」の言葉を思い出しました。祖父も同じことがあったんだな、だから私は学校現場でつらいことがあるけど、頑張るしかないんだなと、すごく思いましたね。
志願者は30倍、偏差値は20近くアップ
――1989年に漆さんが品川女子学園に入られたとき、中等部の志願者数は55人でした。その後、どのように推移しましたか。
漆 5年後、1724人が志願しました。できることをできる人たちでどんどんやって、目に見える成果が出てきます。すると、子どもが喜ぶから手伝おうか、というように教員で価値観が共通してきました。
教師をはじめとして、教育に関わっている方って、みんな教育と子どもが好きなんです。制服図鑑へのPRなど方法論でぶつかっても、生徒が喜ぶと、手伝ってくれるように思考を変えられるんです。教師という共通の土台があるので。
――1989年の偏差値が33。その後、10年で51まで偏差値を上げ、今はもう少し上がっているでしょうか。
漆 大体そのぐらいです。そのぐらいがいいところだと思っています。どうしても中学受験は、「親の受験」の側面も出ます。名門塾に行き、朝から晩までずーっと勉強する。
偏差値は高いかもしれないけど、受験に疲れ、心が追いつかない子も出ます。それよりも、やっぱり多様な心のある人を取りたい。受験で「目の前の合格」は大きく見えるけど、将来の方が長いですよ。他の未来を犠牲にしないでほしいですね。
漆紫穂子さんプロフィール
1961年、東京生まれ。早稲田大学国語国文学科卒、早稲田大学大学院スポーツ科学研究科を経て私立中高一貫校で国語科教員として勤務。1989年から曽祖母が創設した品川中学校・高等学校(現・品川女子学院)に入職し、中等教育の学校運営に携わり、2006年から6代目校長を務める。多くの学校改革や、同校で提唱する「28プロジェクト」などのライフデザイン教育が各界から注目さる。2017年から理事長に就任。
SHARE
記事一覧ページへ戻る