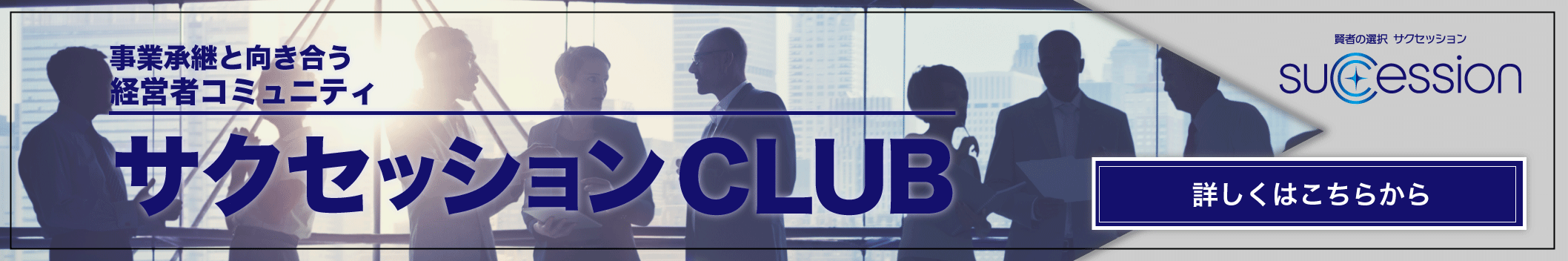COLUMNコラム
幼児教育「七田式」のカリスマを支えた黒子 継ぐ気はなかったけど「あなたが社長をやりなさい」 ~#1【全3回】

幼児教育のメソッド「七田式」の考案者として世に知られる七田眞(しちだ・まこと)氏(1929-2009)。その父が興した「しちだ・教育研究所」(島根県江津市)を引き継ぎ、発展させた息子の七田厚氏に、事業承継にまつわる物語を聞いた。
目次
島根がルーツ、七田式
−−眞氏が、七田式を誕生させて会社を作られた経緯を教えてください。
七田 私の実家は島根県です。私が中学生の時まで、父は自宅で英語塾を開いていましたが、私が広島県の高校に進学した年、英語塾をやめて新しい幼児教育の会社を始めました。
そして私が東京の大学に進んで3年目、新宿にマンションの1部屋を借りて、「しちだ・教育研究所」の東京オフィスを作ったんです。
当時、私は板橋区の3万円ぐらいの安アパートに住んでいました。父から、「新宿御苑の新築マンションを借りて会社をやることになった。夜と週末は誰もいないからそこに来て住まないか」と言われ、ふたつ返事で引っ越しました。1980年代のことです。
−−教育研究所を手伝うことはありましたか?
七田 やはり、何かちょっと手伝わないと悪いかなという気がしました。ちょうどパソコンに興味を持ち、大学でコンピュータ言語を履修していたので、パソコン一式を買ってもらい会員管理みたいなことを始めました。
もう一つ、幼児の英語通信コースがあり、200人くらいのお客さんに教材を送って指導をしました。その二つが、私の最初の仕事でしたね。
私は大学を4年で卒業できず、1年生と4年生を2回やりました。6年生は週に1回大学に行けばよかったので、週40時間は会社で仕事をしていました。父は「しちだ・教育研究所」の東京オフィスに併設し、児童英語研究所という英語に特化した会社を設立。私は専務になりました。
申し訳ないが、継ぐ気は無い

−−当時から事業を継ぐつもりがあったのでしょうか?
七田 学生時代、父から一度、将来自分の仕事を手伝ってくれるかと聞かれたことがあります。その時は「申し訳ないけど継ぐ気はない」と答えました。
親が用意したレールに乗るのは、自分の人生なのに主体性がないんじゃないか、というのが一つ。もう一つは、仕事の内容をあまり理解していなかったためです。父も残念そうではありましたが、無理強いはしませんでした。
−−しかし、24歳で二代目社長に就任しておられます。
七田 大学卒業から半年頃、日本全国に七田式の幼児教室を作るため、「七田チャイルドアカデミー」を作ることになりました。
でも、当時の教材に少々問題がありました。教材を、家内制手工業みたいに印刷担当の社員が機械を回して作っていました。手でカットするので、ちょっと不揃いで。資金も乏しく、現代からしたら考えられないものを売っていました。
今後広く教室ができ、たとえば私の友人たちが七田式の教室に子どもを行かせた時、「お前の教室に入ったけど、あの教材はなんだ」って言われると思いました。
そこで、「教材はこういう風にした方がいい」などいろいろ意見を出しました。専務に就いていたこともあり、他にも会社のことで何度か父に進言しました。すると父は「そこまで考えてくれているんだったら、あなたが社長をやりなさい」。「あ、そう来たか」と思いましたね。
1987年、24歳で「しちだ・教育研究所」のバトンを受けて2代目社長になり、父は会長になりました。父としては、私が社長をやってくれたら、自分は講演活動や執筆活動に専念できる、という考えもあったんです。
著名人の父をプロデュースしていた
−−経営は初心者だった厚さんが、どのように七田式の経営に携わっていったのですか?
七田 父は私に会社を譲った後、3か月後に別の会社を作って社長に就任します。父の講演収入と印税収入は新会社に属し、私の会社は教材売り上げなどを得る仕組みでした。
教育的なことは全て父、私は経営側の黒子に徹する。言ってみれば、七田眞という著名人をプロデュースするような仕事ですね。父が作りたい教材や企画を形にする。20年間一緒に仕事をしましたが、基本は裏方に徹し、表に出ることは極力しませんでした。私自身が幼児教育の講演を始めたのは、父が亡くなってからです。
私は経営者としてはゼロからのスタートでした。学校の先輩に紹介されたコンサルタントの先生には随分お世話になりました。また、税理士と経営状況の話をしたりもしました。20代の私は「何も知らない」という意識が強かったので、頼れるものは頼って知識や情報を得ていましたね。
あとから思えば、父は私が高校生の頃から、経営で大切なことを私にぼそっとささやいていました。覚えているのは「アウトサイダーたれ」。
つまり、人がみんなこっちを向いている時こそ、別の方を向きなさい、そこにビジネスの種があるんだぞ…といったようなことです。私への事業承継を、父はずっと考えていたんだと思います。
しちだ・教育研究所
1978年、七田眞により島根県にて設立。世界の未来を担う子供たちを、大きな志と奉仕の心を持ち、自らリーダーシップを取れる子に育てることを目的とする「七田式」教育を掲げる。1987年、七田厚が代表取締役社長に就任。国内約230教室に加えて、世界16の国と地域に展開。日本発の普遍的な教育として、言語や文化を越えて世界各地で実践されている。
※こちらの記事は追記・修正をし、2024年4月9日に再度公開しました。
#2|「社員教育もできない会社に、子どもを任せられるか!」 1本の苦情電話が、幼児教育「七田式」を変えた
#3|老いた親の経営する幼児教室、継ぐ?継がない? 悶々とする子ども、「七田式」の新たな試み
SHARE
記事一覧ページへ戻る