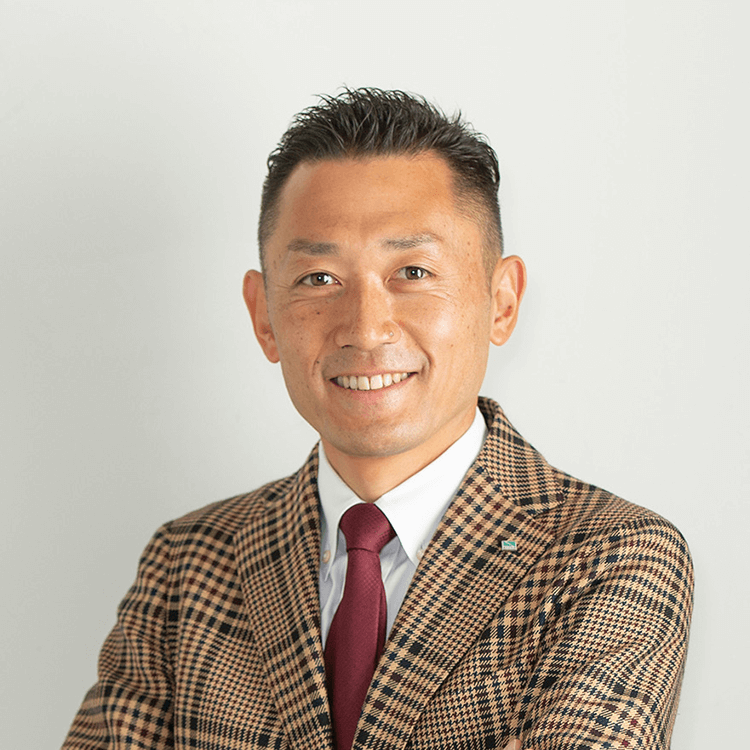「東スポ社員」から、国宝も直す京都の一流美術織物の世界へ 独特の業界用語「全く分からない」、5代目の歩んだ道のり

伝統的な西陣織の世界に革新をもたらし、織物の地位を芸術の域にまで高めた京都の「龍村美術織物」。日本三大祭の一つである祇園祭の山鉾の装飾や正倉院宝物裂の復元など一流の美術品を手掛ける一方、航空機シートやラグジュアリーブランドの内装、「ミッフィー」とのコラボレーション商品など、多様な事業を生み出している。天性の才能と探究心にあふれた初代龍村平藏の「温故知新を織る」精神を受け継ぐのは、五代龍村平藏を襲名した龍村育氏(51)。前職は「東スポ」こと東京スポーツ新聞社の営業職という異例の経歴をもつ龍村氏に、家業を継ぐに至るまでの道のりを聞いた。
目次
「創造」と「復元」が2本柱、ディオールとも取引

─原点である帯をはじめ、文化財の修復や皇室の仕事、航空機のシートなど、事業が多彩です。龍村美術織物はどのような歴史を辿ってきたのでしょうか
1894年、私の曽祖父である初代龍村平蔵が創業しました。古代織物の研究と復元を基盤として、数々の美術品の復元や祇園祭の山鉾の装飾、歌舞伎座の緞帳のほか、国会の議員室の内装、国賓への贈り物なども作ってきています。
初代平藏は、大阪の裕福な両替商の家に生まれましたが、家業が傾いて親戚の呉服店に丁稚奉公したのを機に、織物に興味をもちます。
そこで織物を開発したい気持ちがわき、「一流の織り手がいるのは西陣だ」と考え、京都に出てきたのが始まりです。
古代織物復元の背景には、初代平藏の「誰にも作れない織物を」という考えがありました。複雑で高度な技術が施された昔の織物を研究して習得すれば、これまでにないデザインや風合いの織物が出せる。そこに目をつけ、正倉院や法隆寺の宝物裂の復元を手掛けました。
だから弊社のものづくりは当初から、「創造」と「復元」の二つが事業の柱になっているのです。
初代平藏には、ものづくりの技術や斬新な発想だけでなく、ビジネスの才能もありました。海外にも積極的に出て、クリスチャン・ディオールなど海外デザイナーに向けた生地も制作し、航空機のシートを事業化したのも初代です。
和装以外に空間を彩ったり、文化財の内装を復元したり、多彩な事業があるのは、西陣織の世界に新しい発想を取り入れたからです。
─染織業界を牽引してきた会社ですが、いずれ自分も家業を継ぐだろうという意識は、幼少期からありましたか
家業のことは知っていたけれど、織物に関心はなく、着物を着たこともなかったです。四代平藏だった父は、大学を出て川崎重工のエンジニアをやっていたので、私は神戸で生まれ育ちました。
京都に移ったのは、父が祖父に呼ばれて弊社に入社したときで、私は9歳でした。
初代平藏は子沢山で、後継者以外は商売や機械など別の分野で働くように言っていました。兄弟がみんな織物に集中すると喧嘩になるし、広がりもないと思っていたのでしょう。
祖父は平藏を継がなかったのですが、車好きを生かして自動車事業を立ち上げています。家業としては、和装よりも車のシートの印象が大きかったです。
東スポに入社、致命的にできなかった数学
─織物業界に入る前には、東京スポーツ新聞社に入社しています。まったく毛色が違いますが、なぜその道を選ばれたのでしょう。
車が好きで、中高時代は自動車レースのエンジニアになろうと思っていました。ただ、技術者になるには致命的に数学ができなかった。一方でスポーツも好きだったので、スポーツ記者になろうと。
「記者になるなら東京の大学だ」と考えて上京し、卒業後に東京スポーツ新聞社に入社しました。人間的な部分を探れる面白さがあることも魅力でしたね。
実際には記者ではなく、営業での採用で、広告やイベント企画の仕事をしていました。その頃に学んだのは、何事も一人ではできないということです。人それぞれ得手不得手がありますから。「チームでやる」という感覚は、今に生きています。
─家業を意識し始めたのはいつ頃でしょうか
東スポに入ってからです。マスコミの待遇は良かったけれど、家業の繊維製造業は見るに忍びなかった。社長だった父から、「継いでみるか」という話があったのが、入社して10年ほど経った頃です。ようやくマスコミ業界のことを覚え、自分で立案したことをやっていけるかなと思っていた時期でした。
龍村美術織物はその頃、一度事業を精算し、事業承継に向けて会社の体制を整えていました。銀行から融資が下りたところで私に話がありました。父が四代平藏になる直前です。あまり顔に出さない父ですが、困っている感じがしましたね。
私の生き方に干渉せず、マスコミに入る時も何も言わなかったのに、突然家業の話をされたので驚きましたが、迷うことなく「やってみようかな」と思いました。
「何が楽しいのか」社長の息子じゃなければ辞めさせられていただろう

─マスコミ業界から織物業界に転職された時の印象は
これまでの職場とは180度違っていました。織物を設計する「技術部」に配属されたのですが、社内がすごく静かで、みんな黙々と仕事をしていて。新聞社ではずっとテレビがついていて、人が行ったり来たり、非常に柔らかい世界。
それに比べて、きれいに整頓されているし、定時になるとみんな帰って飲みにも行かない。「何が楽しいのか」と思いました。
けれど、規則正しい生活をしないと織物の設計はできないんですよね。ここでの2年間は、私にとって大きな転換点だったと思います。
技術部が作る設計書に基づいて、原料を買って色を染め、織り手が織っていくのですが、設計の作業は非常に細かい。眠気が襲ってくるし、仕事になりませんでした。
独特の業界用語があって、言葉が全然わからない。ベテランの人に付いて、同じことを1日に何度もたずねるのですが、文句一つ言わずに教えてくれたので救われました。
社長の息子でなければ、きっと「辞めてくれ」と言われていたでしょう。「こんなに難しいことをやっていけるのか」と、不安で悩んでいました。
「ものづくり」と「経営」
─「やっていけそうだ」に変わったのは、何かきっかけがあったのでしょうか
入社1年半から2年ぐらい経った頃でしょうか。なんとか一人で設計書を書いて、試作で織り上がってきたものが形になっているのを目にしたときですね。やっと、織物ができていくイメージができるようになりました。
その後、物流を学んだり、商品を企画したり。社内調整的な役割や常務を経て、2019年に社長に就任しました。父が四代平藏と経営者を兼務していて、「ものづくりに専念したい」となったタイミングでした。
─最初は、経営の部分だけを任されたのですね。当時のことを教えてください
新型コロナの感染拡大が始まった時期で、業績が上がらず、会社として大胆な改革が必要になっていました。産業資材部門の売却など、事業を整理した方がいいけれど、長年育ててきた鉄道事業は工場設備もあるし、父は手放す決断ができなかった。そこで、「自分ではようやらん。社長を交代して舵取り任せるわ」となったようです。
経営を任されることは予想していました。父はものづくりの好きな元エンジニアで、四代平藏に専念することは自然な流れ。ものづくりを指揮する人と経営の責任者は別の方がいい、というのが私の持論でもありました。
本当は、10年ほど経営だけをやり、安定したところで平藏を襲名するかどうか選択したかった。でも、思ったようにはいきませんでした。父が亡くなってしまったのです。
プロフィール
株式会社 龍村美術織物 代表取締役社長 龍村 育(たつむら・いく)氏
1973年、兵庫県生まれ。1996年から2007年まで東京スポーツ新聞社で営業職として働き、父親が社長を務める龍村美術織物に入社。技術部、営業推進部などを経て、2012年に取締役。2016年に常務取締役となり、2019年に代表取締役社長に就任。2024年9月、五代龍村平藏を襲名した。
\ この記事をシェアしよう /









-1.png)
.png)