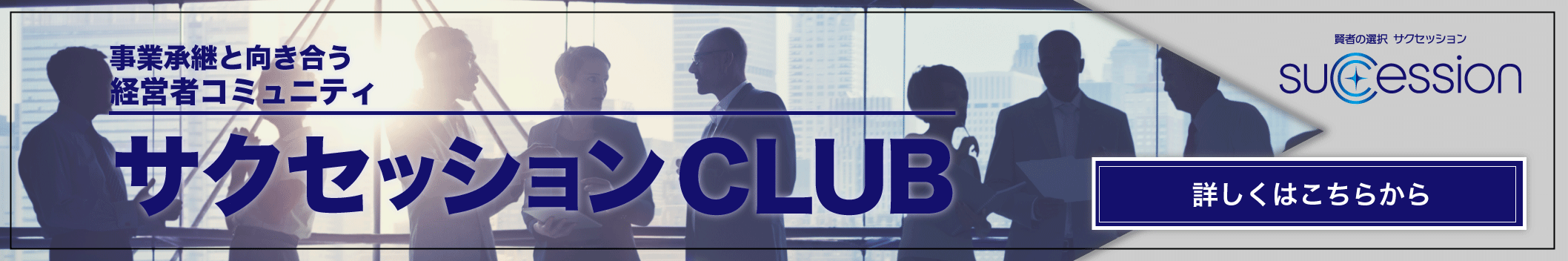COLUMNコラム
「まさか、経営理念がない企業がこんなに多いとは」 将来予測が立たない時代、数字の見通しより「パーパス」が重要に

ここ数年、「パーパス」という言葉を目にする機会が急増した。パーパスとは何なのか。なぜ今、注目を集めているのか。企業の事業承継において、パーパス経営の重要性を説く経営コンサルタント「やまぐち総研」(山口市)の中村伸一所長に聞いた。
目次
そもそもパーパスとは
——パーパス、パーパス経営という言葉はどういう意味でしょうか。
中村 「理念」や「理念を軸とした経営」と捉えていいと思います。組織が存在する意義や目的を明確にして、ビジネス戦略や意志決定の基盤として活用するためのものが「パーパス」です。
——「ビジョン」とはどのような違いがあるのですか?
中村 人によってそれぞれ定義が異なります(笑)。パーパスは存在意義で、ビジョンはマイルストーンを設定し…などと説明していましたが、それではあまりにも堅苦しい。私自身は、細かい定義にはこだわらなくなりました。
「あって当たり前」…じゃなかった
——中村さんは全国でも珍しいM&A・事業承継に伴うパーパス経営のコンサルタントですが、なぜパーパスに注目するのですか?
中村 私は大学卒業後、松下電器産業(現パナソニック)のグループ会社に就職しました。パナソニックグループには、経営活動の指針である「綱領」や従業員の心構えを示した「信条・七精神」があり、会社の理念が全社員に浸透していました。当時の私にとって、理念はあって当たり前の存在だったのです。
ところが、1998年に友人らとITベンチャーを起業し、ホームページ制作を請け負い始めたところ、経営理念がない中小企業が多いことに驚きました。仕方がないので、私たちが大手企業を参考にして顧客企業の理念をつくり、ホームページに記載することがありました。そのころから「理念って、こんなんでいいの?」と疑問を感じていました。
その後、経営理念をコンサルティングしたいという思いが高まり、2005年に「やまぐち総合研究所」を設立しました。当時は起業ブームだったことから、創業支援に携わっていました。「創業者は別に理念なんかいらないんじゃないか?」と言う人もいますが、創業には事業への思いが必要です。その思いが理念になるのです。
軸がなければ、事業の承継・再構築がブレる
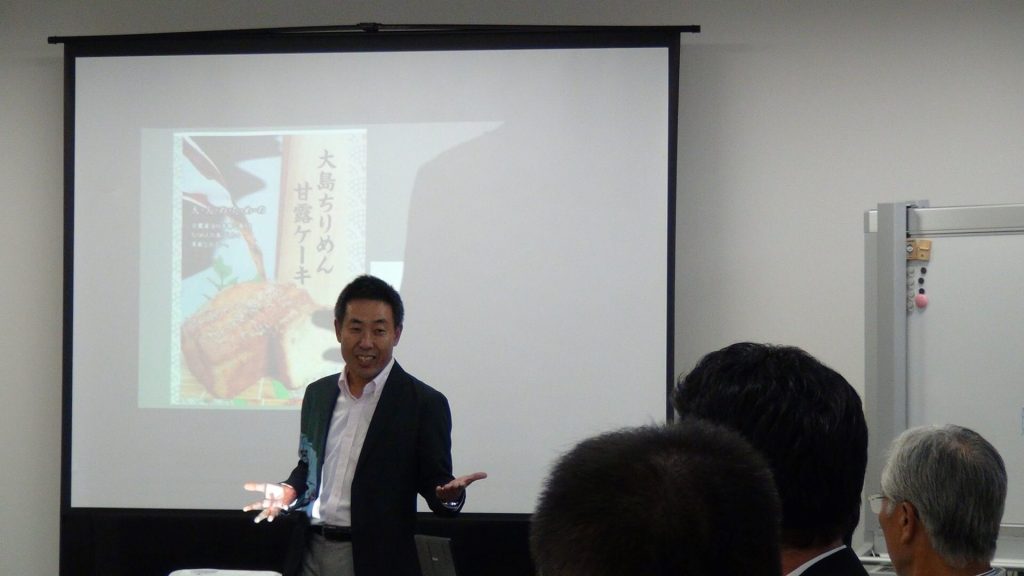
——経営における理念の重要性はどんなところにあるとお考えですか?
中村 新型コロナウイルス禍によって将来の予測が立たないVUCA(ブーカ)時代になったといわれます。会社経営の方針を立てようにも、数字的な見通しを立てにくくなりました。だからこそ、ずっと残る経営の軸として、理念の重要性が高まっています。
私は理念経営には以前から注力していましたが、パーパスという言葉を使うようになったのはここ2年くらいです。コロナ禍で改めて理念を勉強したとき、大手企業がパーパスという言葉を使うのをよく耳にするようになったのがきっかけです。
コロナ禍では、国が「事業再構築」の支援を打ち出しました。ポストコロナを見据え、新分野への事業転換・再編を後押しするというものです。
しかし、中小企業が何でも手を出すと、事業が雑多になって収拾が付かなくなってしまいます。事業を再構築するためにも、改めて経営理念を見直して、新しく始める事業を組み立てるべきです。
——確かに、会社として大きな軸があればブレれずに事業を多角化できると思います。
中村 コロナ禍では、私は「跡継ぎ支援」にも取り組みました。跡継ぎの方々と会っていると、「親の理念やビジョンをいかに引き継ぐか?」「新たに自分たちが理念をつくるべきか?」といった課題にぶつかっていました。
VUCAの時代に対応し、事業再構築や事業承継を進めていくためには、理念・パーパスが必要だと思います。ただし、「古くからの理念」と「新しいパーパス」にはつくり方や実践の仕方に大きな違いがあります。
経営者が考える「理念」、社員みんなで創っていく「新しいパーパス」

——どのような違いですか?
中村 経営理念は、経営者が自分で考えて、自分の会社のためにつくるのが一般的です。それを従業員に浸透させる流れです。
一方、パーパスは、経営者が社員、場合によってはもっと広くステークホルダーと一緒に作り上げるものです。経営者が1人で考えるのではなくて、会社全体の思いを反映させるように変わってきたのが「新しいパーパス」だと思います。
——全社員参加ですか?
中村 できれば全社員でつくるといいと思います。規模が大きな企業ならグループ分けが必要ですが、20〜30人の中小企業なら全社員参加のミーティングを開けます。
たとえば、商工中金は2022年3月、経営層や現場社員が一丸となってパーパスを制定しました。ワークショップには4000人以上が参加したそうです。
——どのようにパーパスを創っていくのでしょうか。
中村 まずは現行の経営理念・ビジョンを再理解して、経営資源や課題を棚卸しします。それらを踏まえて、30年後、40年後、自分たちの会社はどのようになっているべきか、全員の意見を吸い上げて、パーパスにまとめていきます。
社員を巻き込むワークショップ形式でつくれば、押しつけなくても自然に浸透しているというメリットも大きいですね。
中村伸一さんプロフィール
やまぐち総合研究所有限会社 取締役所長。1965年、山口県山口市に生まれる。九州産業大学卒業後、中国松下システム(株)に入社。友人3名とIT関連事業を行うキャスト(株)を設立。取締役として2年、代表取締役を5年間つとめる。2005年、やまぐち総合研究所有限会社を設立。企業の事業づくりを支援する達人として、コラボレーションを事業創造の中心に考え、「ワクワクコラボレーション」を商標登録して「ワクワク」する事業創造の支援をしている。
SHARE
記事一覧ページへ戻る